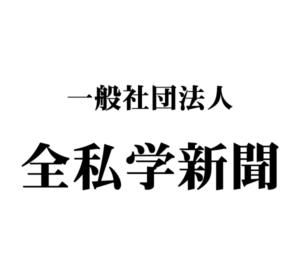全審連が文科省に要望書を提出
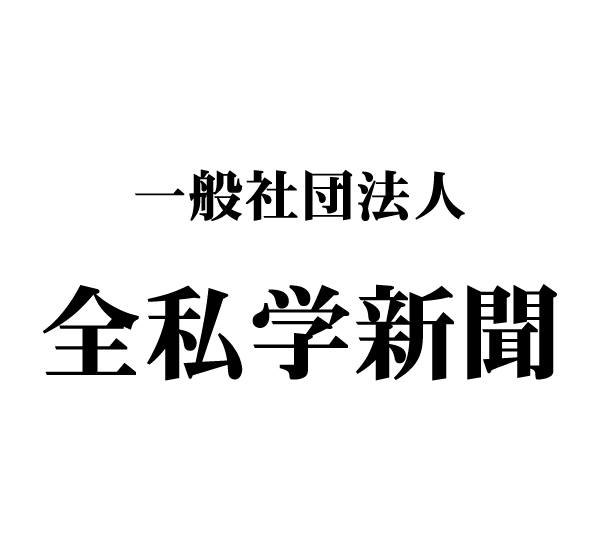
広域通信制高校の問題改善など要請
全国私立学校審議会連合会(近藤彰郎会長)は3月27日、文部科学省のあべ俊子大臣を始めとする政務3役、藤原章夫事務次官、西條正明官房長、望月禎初等中等教育局長、浅野敦行高等教育局私学部長等に「広域通信制高等学校に関する問題の改善等について」と題する要望書を提出した。同連合会は毎年秋に各都道府県の私立学校審議会委員と所管部局の職員が出席して総会を開き、私立学校行政が直面する課題について協議・情報交換を行い、その中で国や都道府県等に要望すべき事項があると、要望書にまとめ提出している。
同連合会は20年以上にわたり、広域通信制高等学校の不適切な運営状況の改善や実情に合わない制度の見直し等を求めてきたが、昨年10月、長野県で開かれた全審連総会でも各都道府県が抱える課題等が明らかになっており、今回の要望書はそうした課題を整理して作成された。
要望事項は大きく分けて次の5点。
(1)定通振興法の改正及び高等学校通信教育規程における特例措置の見直し。同法の前提となっている勤労青年に対する教育の機会均等の保障が時代と共に大きく変化した中で、全日制課程と比べて学校施設・設備、教員の編成、教育課程の基準等が特例的に緩和されていることの見直しが必要なこと。
(2)広域通信制高等学校の指導監督の在り方の見直し。全日制・定時制課程と判別がつかない通学コースを有する学校が多く設置され、所轄庁の圏域外に通信教育連携協力施設を設置し、日常的な教育活動を実施している一方で、所轄庁がこれら施設を調査する体制は不十分であること、また全審連総会で、収容定員が数千から数万規模の巨大な広域通信制高等学校については、文科省が先導的な役割を果たし、所轄庁による管理を主導すべきだとされたことから、指導監督の在り方を見直すよう求めている。
(3)設置認可基準等の策定の促進及び標準例の趣旨の周知徹底。都道府県によって設置認可基準が策定されていないことや、標準例の解釈・運用が区々で、趣旨が徹底されていないため、文科省が所轄庁や設置者を継続的に指導すること。
(4)広域通信制高等学校による生徒募集等の是正。一部では実施校だけでなく、通信教育連携協力施設において入学者選抜等が所在する都道府県に先駆けて行われていることから、適切な時期での実施の徹底、中学校段階の通信制フリースクールがあたかも学校教育法上の中学校と誤解されかねない不適切な広告・表示を行っている事例に対する指導、また広域通信制高等学校の設置認可について、設置認可県における公私の収容計画とかけ離れた無計画で根拠のない収容定員が設定されている現状を見直し、実質的な収容定員の上限規定を設けるよう要請。
(5)全日制高等学校の教育課程の在り方の検討。全日制課程が社会の多様化や高度化に柔軟に対応できるよう、中教審の教育課程企画特別部会で教育の自由度を高めるための方策を議論すること、国公私立の役割分担についても議論を進めてほしいと要望している。