2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議始動
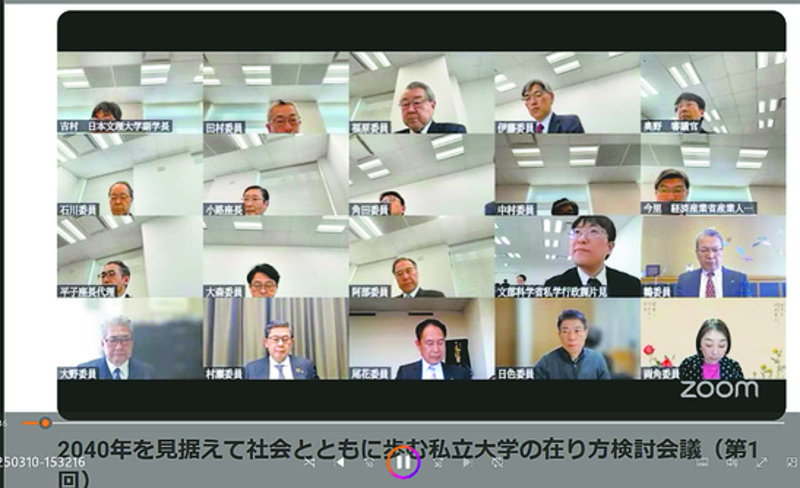
初会合開く 地域における私大の取り組み等を聴取
人材育成での役割など巡り意見交換
中央教育審議会が2月21日に、2040年の社会を見据えて「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~」と題する答申を、あべ俊子・文部科学大臣に提出したのを受けて、同省の藤原章夫・事務次官は同日、「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」を新たに設置することを決め、その第1回会議が3月10日、文科省でオンラインも併用して開催された。
同会議は、日本の高等教育を支える私立大学が、教育の質を高め、地域や経済界を始めとした関係者と協働しながら、人材育成を充実し、それぞれの役割を、ますます果たすことが期待されている中で、「知の総和向上」答申の方向性に基づき、私立大学を取り巻く環境の変化を見据えつつ、私立大学の振興に向けて、私立大学が期待される役割を明確化し、その役割を果たしていくための具体的な方策等に焦点を当てて検討するのが目的。
検討事項としては、(1)地域の人材育成に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方など具体的な方策、(2)急激な少子化を見据えた大学経営の在り方、(3)国際競争力の強化に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方など具体的な方策、(4)私立大学における教育・研究の質の向上、(5)その他―の5項目が想定されている。
委員は阿部守一・長野県知事、石川正俊・東京理科大学長、伊藤公平・慶應義塾長、大野博之・国際学院埼玉短期大学理事長・学長、大森昭生・共愛学園前橋国際大学長、尾花正啓・和歌山市長、角田雄彦・上智大学大学院法学研究科教授・弁護士、小路明善・アサヒグループホールディングス㈱取締役会長兼取締役会議長・日本経済団体連合会副会長、田村秀・長野県立大学グローバルマネジメント学部教授、鶴衛・学校法人鶴学園理事長・総長、中村和彦・国立大学法人山梨大学長、日色保・日本マクドナルド㈱代表取締役会長、平子裕志・ANAホールディングス㈱特別顧問、福原紀彦・日本私立学校振興・共済事業団理事長、村瀬幸雄・岐阜県商工会議所連合会長・㈱十六フィナンシャルグループ取締役会長、両角亜希子・東京大学大学院教育学研究科教授の計16人で、大学での人材育成等にとって支援や連携が不可欠な地方自治体の首長、経済界関係者の他、私立を中心に国立、公立も加えた大学関係者等で構成されている。このうち座長は小路氏、座長代理は平子氏で、二人とも経済界関係者。また会議には経済産業省の今里和之・経済産業政策局産業人材課長も出席していたが、文科省では関係省庁と連携して「知の総和向上」を目指していく考えだ。
この日は初会合ということで、文科省高等教育局私学部の三木忠一・私学行政課長が、中教審の「知の総和向上」答申の要旨(本紙前号3面参照)と私立大学に関する現状等として、(1)私立大学の概況と少子化等の私立大学を取り巻く環境、(2)私立大学が果たしている役割、(3)都道府県別や地方の大学に関係する資料、(4)高等教育に関する財政措置と私学助成の現状等について説明した(本紙3面に関連図表掲載)。
私立大学の現況等に関しては、18歳人口が減少し続ける中にあっても大学進学率は微増(2022年は56・6%、2050年は60・2%)する見通しだが、2026年に大学進学者数がピークを迎え(約63万人)、以降、減少局面を迎え、2043年には42万人となり、以降2050年まで横ばいの状況が続く見通し。また地域の私立大学が地元の多くの若者の受け皿となっており、県内就職率も国公立大学と比べ高く、また私立大学が地域にとって不可欠な警察官や看護師、保育士、薬剤師等のほとんどを輩出していること、私立大学が経営悪化から公立大学化すると地域内入学率や地域内就職率が下がる傾向にあることなどを説明した。
その後、有識者からのヒアリングが行われ、伊藤彰浩・名古屋大学教授は「近代日本の高等教育、私立高等教育機関の発展」と題して、財政基盤の脆弱な私立の専門学校が高いハードルの大学昇格を目指して社会ニーズに敏感に対応、一部に営利主義や非常勤講師への高い依存も見られたが、大正時代頃から官立より高い授業料が取れるようになったことなどの歴史を紹介。吉村充功・日本文理大学副学長が地域と連携した同大学の実践や、おおいた地域連携プラットフォームの活動などを説明した。また大分県総務部学事・私学振興課が若者の県外流出抑制、多様な主体との連携による地域課題の解決、人材育成、県内産業の振興のため、県として大学連携に取り組んでいること、大学連携に関わる事務を、令和6年度から総務部学事・私学振興課に集約、単年度で約1800万円の関連予算を計上していることなどを説明した。
続いて地域の人材育成に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方等具体的な方策についての意見交換が行われ、その中で(1)尾花正啓委員(和歌山市長)から、若年層の県外流出、まちなかの人口減少、専門人材(看護師、理学・作業療法士、薬剤師等)の不足から大学誘致(小中一貫校閉校に伴う学校跡地の有効活用、国費も活用して市による財政支援)で県外進学率ワースト1を脱却(47位↓41位)するなどの成果が表れていることなどを報告。また(2)大森昭生委員(共愛学園前橋国際大学・同短期大学部学長)が自治体・産業界・近隣の大学等との連携や、地域政策を支える大学・地域政策と歩調を合わせる大学としての取り組みなどを紹介。(3)鶴衛委員(学校法人鶴学園理事長・総長)が広島工業大学における産官学連携しての地域の基盤人材育成の取り組みを報告。(4)中村和彦委員(国立大学法人山梨大学長)が大学連携推進法人を活用した連携事業(大学アライアンスやまなし)を説明。(5)地方自治の研究者の田村秀委員(長野県立大学グローバルマネジメント学部教授)が私立大学の公立大学化については様々な課題(地元高校卒業生の入学者数減少、地元就職率の低下、自治体は高等教育に関する政策・ビジョンを持っているかなど)があり、慎重や検討が必要なことや、首長の交代による方針転換などの懸念もあることなどを説明した。
その後、大野博之、大森昭生、角田雄彦、中村和彦の4委員が作成した論点整理(私立大学が果たす役割、地域の人材育成に向けた私立大学の在り方)が小路座長から説明され、委員による意見交換が行われ、最後に小路座長は産学連携ではなく産学融合が重要で、大学の収入の多様化、高度専門人材の育成など産業構造の変化を踏まえた検討、地方・中小への労働移動の実現や大学の数をどうしていくのかも課題との考えを示した。次回・第2回は4月中下旬に開催予定、急激な少子化を見据えた大学経営の在り方を検討する。


