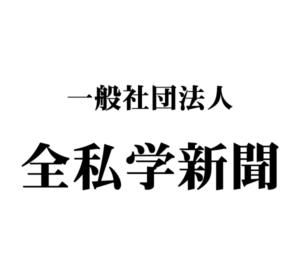第4回2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議

「中間まとめ」案を了承
地域人材育成担う地方大学を重点支援
日本の競争力を高める大学を重点支援
経営指導行う法人を100法人程度に拡大
文部科学省の「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」(座長=小路明善・アサヒグループホールディングス株式会社会長)は7月28日、文部科学省でオンラインも併用して第4回会議を開催した。
冒頭、7月15日付で就任した小林万里子・高等教育局私学部長があいさつし、「私立大学の重要性は増している。本日は中間まとめをすると伺っている」などと語った。
この日の議題は、「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ」と題した審議の中間まとめ(案)についての審議。これまでの審議は今年2月の中央教育審議会のいわゆる「知の総和答申」をベースに行われていて、答申との重複を避ける意味で、ポイントを絞ってまとめられたのが今回のパッケージ。
その中で私立大学を取り巻く環境については、出生数の減少により相当数の法人が縮小や撤退をよぎなくされることを覚悟しなければならないこと、地方の小規模私立大学から撤退する可能性があること、我が国の理工系入学者の割合はOECD平均よりも大幅に低いことなどを指摘。
そうした中で学部学生の約8割の教育を担い、エッセンシャルワーカーや産業人材等の育成、国際競争力強化に資する研究振興、地域創生などさまざまな観点で重要な役割を果たす私立大学の教育研究の充実は、「知の総和」の向上に資するとともに、経済社会・国民生活の向上にも貢献しており、基盤的経費をはじめとする支援の拡充は不可欠であること。その上で、(1)地域から必要とされる人材育成を担う地方大学の重点支援への転換、(2)日本の競争力を高める教育研究を担う大学への重点支援への転換、(3)再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転換―の3つの施策の方向性の転換を提言。このうち(1)では産官学等が協力しての人材育成に係る取り組みへの支援、地域の人材需要や産業ニーズ等に応じた教育研究を行う私立大学に対する私学助成のメリハリ・重点化等を推進。(2)では優秀な研究者を確保するための高額給与に係る私学助成の減額の仕組みの見直し等を、(3)では経営指導の強化等、学校法人間の連携・合併、円滑な撤退に向けた支援等、学部等新設の厳格化等の方向性を打ち出している。
こうした中間まとめ案に対して検討会議委員からは、「大学分布の偏在、大都市部での私立大学集中の課題に関する記載は少々もの足りない。大学の立地そのものの在り方の議論が必要。また大学が安定して経営できる方向性も論点にしっかり位置付けてほしい」「(2)の日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援への転換」については、審議中の令和8年度からの次期科学技術・イノベーション基本計画に反映してほしい」「大学を先導してきたのは私学の自主性・独自性であることをしっかり述べることが必要。必要なことではあるが地域人材の育成に集中しすぎているのではないか」「私立大学は国立大学の補完だったとの記述は(そうした面とそうではない面と)両方あるので、補完との記述は見直してほしい」「国際競争力の強化という観点では指定私学という考え方があってもいい。その場合国立大学並みの支援が必要」「経営指導の強化等の箇所では、学校法人の経営力を強化するため資産運用による財源の多様化を推進するとあるが、かつて資産運用に失敗した私大があった。ミスリードにはならないか」「高等専門学校で大学編入希望者がどんどん増えている。地方の大学はそうした編入学希望者をどう受け入れていくか考えるべきだ」などの様々な意見が出された。最終的には小路座長が「可能な限り意見を反映していきたい。修文については座長と事務局に一任願いたい」と語り、了承された。
その後は、名古屋商科大学の栗本博行学長が「国際認証を通じた教育研究の質向上」との取り組みを徹底し今や75カ国から留学生を受け入れ、また教授陣も国際化していること、立地の悪さを逆手にとって住めるキャンパスを整備することなできたことなどを報告した。また金沢工業大学の大澤敏学長が「金沢工業大学の教育・研究の特色~地域の人材育成・国際競争力の強化を通した教育・研究の質の向上~」と題して発表を行った。その中では数理・データサイエンス・AI教育プログラムや、社会実装型のコーオプ教育、イノベーション教育、国内外での多様な連携・共同研究拠点の国際化等の取り組みを紹介、教員の出身はアカデミアと産業界が半々で、産業を通して大学のグローバル化を進めていることなどを報告した。次回以降の検討会義では「私立大学の教育研究の質の向上」について審議するが、それに先立って2大学の教育・研究の向上に向けた取り組みを聴取、議論については次回に行う予定。次回は9月26日(金曜日)に開催の予定。