中教審第152回教員養成部会開催
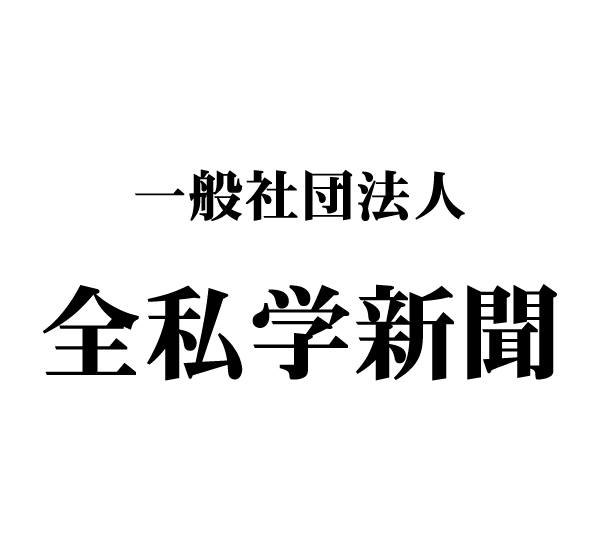
社会人の参入しやすい教員免許制度等を検討
英国の取り組みも聴取
中央教育審議会初等中等教育審議会教員養成部会(部会長=秋田喜代美・学習院大学教授)は7月17日、文部科学省でオンラインも併用して第152回部会を開催した。
今回は、多様な専門性・背景を有する社会人が教職に参入しやすい制度の在り方について話し合われた。文科省から、特別免許状の活用などの説明があった。
大学院で教員免許状を取得するには、大学の学部で教職課程を履修していなかった場合には、大学院で開設されている科目に加え、学部の教職課程の履修が必要で、教育実習もあり、2年間で終わらせるのは難しい現状がある。普通免許状を持たないが、知識・経験を持つ社会人などに授与される特別免許状は、授与件数は増加傾向にあるものの、制度の趣旨がなお広く理解されず、運用が積極的でない自治体があるのが現状だ。
企業に在籍しながら教師として勤務する方策として、神奈川県川崎市で富士通株式会社が川崎市教育委員会と包括協定を締結し、シニア人材を語学などの特別非常勤講師として勤務させる事例、東京都中野区の私立・新渡戸文化学園で、多様な背景の教職員集団を形成するために約4割の教員が兼業者である事例が紹介された。
次に松田悠介委員は、理事を務める認定NPO法人Teach for Japanの、社会人を教職に入職させる「フェローシッププログラム」を紹介した。同プログラムは多様な経歴を持つ社会人などの教員志望者を選考し、研修後に2年間教師として学校に送り出すもの。同法人では民間企業を競争相手と考え、中途採用市場として年に3回の入職機会を設けている。応募から内定までの期間はわずか1カ月。学校に派遣される期間は自治体から給与が支払われ、赴任中も同法人がオンライン研修やメンタルヘルスサポートを行う。これまでの経験から、松田氏は、臨時免許による入職型試験を認める新しい教員資格認定試験の導入、民間の認定団体も大学と並列とし、資格認定試験の事務局となるような制度改正を提案。
また植田みどり氏(国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括研究官)は英国の大学院レベルの教員養成について話した。英国で教員養成プログラムを提供する主体は多様で、170機関が認定されている。大学院レベルで教員資格を取得できるプログラムにはPGCEがある。PGCEでは教科に関する知識、教授技術、対人スキルを学び、24週間、最低2校で実習を行う。修士課程で適用できる単位が取得でき、教員が不足する教科のコース、貧困地域での教員養成を選択する人は学費が無料となる。
さらに英国にはサプライ・ティーチャーの仕組みがあり、病欠や研修などで教員がいない場合に臨時で派遣される。直接学校、地方当局に雇用される場合と民間派遣会社に雇用される場合があり、50~60代が多く、80%が教員資格を所有していて、柔軟な働き方を希望してサプライ・ティーチャーを選ぶ人が多い、という。報告の後に行われた審議では、サプライ・ティーチャーに関心が集中、「サプライ・ティーチャーは日本にもあると助かる。文科省でモデルを示してほしい」「サプライ・ティーチャーは、日本で課題となっている空きコマを確保するためにも利用されているのか」などの意見が出された。植田氏は「英国では空き時間の確保には、サポートスタッフやTAが配置される。サプライ・ティーチャーはすぐに動ける人材をストックしておく仕組みと考えられており、民間派遣会社では、人材を常にトレーニングして、サービスを利用してもらえるように質管理に努めている」と説明した。
企業に在籍しながら教師として勤務する形に関して「シニア人材を派遣して、学校、企業とも社会人の教師登用のメリット、デメリットを理解し、社会人登用の良さを実感した上で、現役世代の従業員に拡大していくのが現実的ではないか」という意見が出された。令和7年度教員免許状授与の所要資格を得させる大学の教職課程の認定について、70大学、99学科、285課程から申請があり、文科大臣から中教審に諮問があったとの報告がされた。


