文科省検討会 第三次取りまとめ案を承認
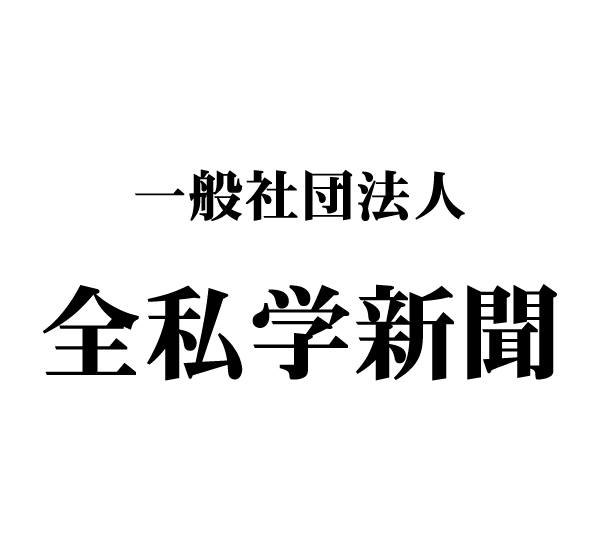
大学病院改革の事例報告
教育改革論議の動向
文部科学省は6月24日に第15回今後の医学教育の在り方に関する検討会(座長=永井良三・自治医科大学学長)を、同省内でオンラインを併用して開催した。大学病院改革の取り組みについて2件の発表が行われた。
藤田医科大学(愛知県)は臨床研究を推進する取り組みと大学病院改革プランについて話した。
同大学は文科省の「高度医療人材養成拠点事業」に採択され、次世代の臨床研究エキスパートを育成するため、優秀な学生を選抜し、学部生からSA(Student Assistant)として臨床研究に携わらせている。研究に従事した時間は雇用と見なし、学生には責任が求められる。
J―PEAKS(地域中核・特色ある研究大学強化促進事業)では、アカデミアからの創薬を目指し、ヒト、モノ、カネが循環する持続的な創薬エコシステムを確立する。大学発のスタートアップ・ベンチャーキャピタルを創設し、有望なスタートアップ企業を支援する。医師の労働時間適正化の推進と大学病院の教育・研究・診療の役割・機能の維持の両立を図るため大学改革プランを策定し、2029年度までに取り組む運営改革、教育・研究改革、診療改革、財務・経営改革を掲げている。
国立佐賀大学医学部附属病院は、病院運営の支出削減と収入増加の方策について発表した。物品購入では他病院の購入価格を調査して、価格交渉をし、光熱費を下げるためにベンチャー企業にエネルギー効率最適化を依頼するなどして経費軽減に努めていることなどを説明。また、各診療科の状況を分析し、医師、病棟師長、看護主任にヒアリングを行い、診療実績を上げるための情報提供と助言を行う。一例として、他の病院と比較した平均在院日数と粗利単価の関係を示したグラフを作成し、医師たちに見せてヒアリングし、改善策を検討し、半年後に再びヒアリングすると、在院日数が短縮され、粗利単価が上がっていると確認された、と報告した。
続いて同検討会の第三次取りまとめ案が文科省から説明された。
第三次取りまとめ案では、大学病院が物価や光熱水費の高騰、人件費の増加によって破綻しかねない状況となっていることが強調されている。
大学病院の機能等別の対応方策としては、(1)運営、財務・経営改革では、診療科別病床数や人員配置など医療資源の再編・見直しを含めた事業規模の適正化、運営費交付金、経常費補助金等の基盤的経費の確保、診療報酬の財源等多様な財源の確保、最先端の医療機器等整備の支援の着実な実施等を挙げた。
また、(2)診療改革では、医師の研究時間の確保には診療にかかる負担を軽減する必要があり、他の医療機関・薬局との間で必要な電子カルテ情報や医薬情報の円滑な共有ができる支援、業務の移管やシェアができる環境整備推進などを挙げた。
(3)地域医療への貢献では、大学病院の機能を把握し、実際に行っている診療や地域医療への貢献を制度上どのように位置づけるのか検討が必要と指摘している。
(4)研究改革では、研究者の流動性・多様性が図られるよう研究者間や組織間の連携の課題整理を行うこと、各大学の産学連携の取り組み事例の紹介、横展開を通じ、イノーベーションマインドの涵養の推進などを挙げた。
(5)教育改革では低年次から多様な実習を推進し、総合的な診療能力をもつ医療人材の育成を促進する、実習を指導する医師に、国から臨床実習指導医(仮)の称号を付与する仕組みの具現化、医学生、大学院生がTA・RA(Teaching Assistant,Research Assistant)として教育研究に参画できる機会創出の重要性を指摘した。
取りまとめ案に関して審議され、「大学病院の経営状況が苦しく、教育や研究に時間を割けなくなっている」と根本的な課題が指摘された。また、「研究時間が確保できたら研究が増えるとは思えない。医学生は研究そのものに魅力を感じていないのではないか。医学の中に閉じることなく、理工や人文社会分野にもフィールドを広げていくような研究面の改革も必要ではないか」という研究内容の改革を訴える発言も出された。
また「病院情報システムのシステム更新費用が高騰しているが、ここには補助金がつかない。AIの導入も業務効率化には必要だが、実務の方に経費が優先されてしまう。AI化への支援体制も必要」というDXの強化に財政的支援を求める意見も出された。
第三次取りまとめ案は委員から了承され、修文などは座長一任とされた。


