中教審第9回デジタル教科書推進WG開催
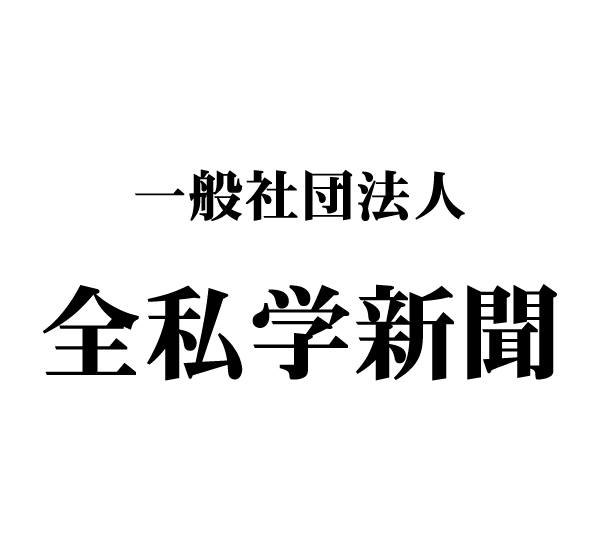
デジタル教科書導入の制度面検討
検定の対象範囲など3論点を中心に
文部科学省中央教育審議会・初等中等教育分科会は6月12日に同省でオンラインも活用してデジタル教科書推進ワーキンググループ(主査=堀田龍也・東京学芸大学教職大学院教授)の第9回WGを開催した。
今回の議題はデジタル教科書の導入の制度面の検討で、文科省は論点として、(1)新たな学びに対応した教科書の在り方、(2)検定の対象範囲やデジタルの機能の扱い、(3)デジタルな形態の教科書の採択の3点を提示した。
論点(1)は、新たな学びに対応した教科書の使用をどう考えるか。
教科書は教科の主たる教材であり、何を教えるかは学習指導要領に基づき学校や教員の裁量に基づく多様な創意工夫が前提とされている。教科書には発展的な学習内容など多様な情報も含まれていることを考えれば、教科書は網羅的に一律に指導する必要はない。
教科書の使用は、学びの在り方に応じて変わるもので、個別最適で協働的な学びにつなげるために、教科書の使用にどのような取り組みが考えられるか。
論点(2)は、検定の対象範囲やデジタル機能の扱い。
新たな学びに対応する教科書は、中核的な概念をつかむことに重点を置き、内容・分量を精選し、教材は教科書で得た理解を更に広げ、深めるための情報を得る手段とする役割分担が考えられる。その上で、デジタル技術を導入し、教科書自体はシンプルで軽いものとし、多種多様なデジタル教材を効果的に組み合わせ個別最適で協働的な学びの実現を図る仕組みに変えていく。
これは検定に重要な視点となるのではないか、としている。
学習内容の理解に役立つと認められる本文・図面の動的表示機能、音声読み上げ、色の変更などの機能は教科書のデジタル機能として整理し、検定審査では本文などの関連性など限定した範囲で確認することにとどめるのはどうか。
デジタルの良さを生かすために、教科書の内容を動的に表示させ、操作できる機能の扱いについても検討が必要ではないか。
教科書のデジタル部分の具体的検定方法やどのようなデジタルコンテンツが教科書のデジタル機能に相当するかなど検定上の取り扱いは、教科用図書検定調査審議会で専門的見地から審議を行うことが必要ではないか。
論点(3)では、何をもとに採択するのかをテーマとし、デジタルの形態が教科書として認められた場合、教科書見本として採択権者の教育委員会などに示されるものは、実際に供給・配信される教科書と同等のものを同じような方式で供給・配信し、それに基づいて採択するのが適当か。
採択事務の負担を軽減するため、デジタル機能を一覧表で示す、実務ルールを作成し、説明機会を設けるなどの方策が考えられるか。
その後、委員による論議では、教科書を網羅的に教えることにとらわれる現状に対して、「『教科書“を”教える』のではなく、『教科書“で”教える』ことが基本」、「教科書は学習指導要領の内容を深めるもの」など、網羅的な指導を疑問視する意見が複数の委員から出された。
また、「論点(2)で『教科書のデジタル機能の検定審査は本文等との関連性など限定的な範囲で一定の確認を行うにとどめる』としているが、限定的な範囲とはどこまでを指すのか、確認はどの程度の強制力を持つのか、今後、明確にする必要があろう」という意見も聞かれた。
教科書発行会社サイドからの意見としては、「発行者としてはデジタル教科書の検定基準が気になる。例えば『内容の効果的な理解に役立つと認められる』という場合、効果的の判断をどう考えるのか、具体的な例を検討してほしい」という意見が出され、「デジタル機能は教育の質の向上に資するもので、デジタル機能が追加されて教科書の準拠性、公正性、正確性が損なわれることはないので、デジタル機能に検定は必要ないのではないか」という発言もあった。
最後に堀田主査が、「今後は、もう紙かデジタルのどちらかが適切かの議論は避けたい。紙とデジタルの両方の形態を持つものを教科書とし、その際にデジタル部分の検定をどうするかという話だ。次期学習指導要領の改訂では教育課程の弾力的な運用が検討されているので、子供一人一人、個々の学校の特徴に合わせた教科書の供給の在り方もこの会議で検討したい」と語った。


