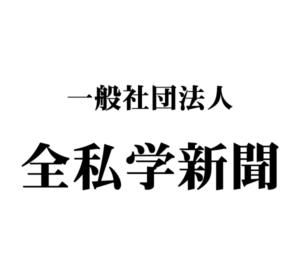第2回地域大学振興有識者会議を開催
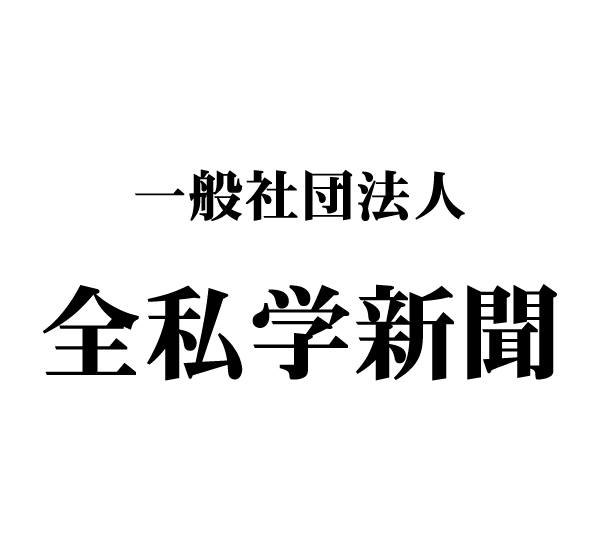
エッセンシャルワーカー養成実情等を聴取
県内養成が危機的状況も
文部科学省の地域大学振興に関する有識者会議(大森昭生座長=共愛学園前橋国際大学・短期大学部学長)は6月10日、同省でオンラインも併用して第2回会議を開催した。同会議は中央教育審議会の「知の総和向上」答申の提言等を踏まえ、地理的観点からの高等教育へのアクセス確保や地方創生など地域大学振興の在り方について総合的に議論するため今年4月に新設された会議。
2回目の今回は、議題(1)として、長谷川知子・日本経済団体連合会常務理事、髙市邦仁・三井住友フィナンシャルグループ社会的価値創造推進部長、小林浩・リクルート進学総研所長の3人の同会議特別委員がこれからの高等教育の在り方や地域の産業人材の育成などについて意見を発表、意見交換が行われた。
この中で長谷川氏は、「大学は地域の産業を支える知の拠点として、地域の産業政策と教育政策を連動させつつ、地域振興の担い手を育成・輩出することが求められており、急激な少子化の中で大学の連携・統廃合と「出口の質保証」が急務なことなどを指摘。また髙市氏は大学とともに進める新しい産学連携を提案、そこでは社会課題を起点にしたテーマを設定、オープンイノベーションにより共同で研究、発信、社会実装を行い、利益を大学と個別企業の二者だけのものとせず、社会や地域等も利益を得ることができるようにすることが重要で、その中で金融機関は大学の変革を支えること、大学と各ステークホルダーをアグレッシブに繋ぎ、次代を担う学生、研究者を応援する役割を果たすべきだ、とし、SMBCグループが現在進めている筑波大学や京都大学等との連携事業等を紹介した。
さらに小林氏は地域ごとに産・官・学・金(融)の合同で、中長期的視点に立ち地域の産業を検討するプラットフォームの構築を行い、そのプラットフォームと連携した地域の大学等連携推進法人の枠組みと機能を強化すること、地域間留学(国内留学)制度等により人材流動性の確保と滞在・関係人口の増加を図ること等を提案した。大森座長からは地域の産業で求められている人材を炙り出す難しさが指摘されたが、長谷川氏は「中核都市を中心に県域を越えた広域経済圏ごとの成長産業、人材を考えるべきだ」と回答。しかし大森座長は「広域経済圏で誰がリーダーシップを取るのか」と語るなど問題解決の難しさを窺わせる場面も見られた。
続いて議題(2)として同省から地域に不可欠なエッセンシャルワ―カー養成の一例として幼稚園教諭・保育士養成課程に係る地域アクセス確保に関する課題等が説明された。令和5年度の幼稚園教諭の免許授与件数は短大で1万5516人で、大学の1万4243人を上回っており、また保育士資格取得者の46%が短大卒業者だが、少子化が進む中で短大の学生募集停止(予定)が令和7年度、8年度とも23校に達し、県内唯一の短大が閉校することになって今後の地域での保育士養成の在り方について対応を検討する自治体も出ていることなどが報告された。
福井県では幼稚園教諭・保育士資格を取得できる機関が仁愛大学・仁愛女子短期大学のみになる見込みで、第2回会議では同短大の石川義昭副学長等と卒業生、学生がオンラインで出席し、同校の取り組みや人材育成への思い、卒業生、学生の考えなどが語られた。地域の保育ニーズは高いものの、定員割れの状況が続いており、同校では保育職の魅力を県内高校生等に向け様々なメディアで発信していることなどを説明。卒業生や学生からも教員等の手厚い支援等が勉学を続ける力になったこと、卒業後は地元からの求人が多かったことも良かった点などの発言があった。その後、文科省とこども家庭庁から幼稚園教諭や保育人材の確保に関する取り組みが説明された。議題(3)では第2回以降個別に議論が必要な事項が同省から以下の通り説明され、意見交換が行われた。(1)地域構想推進プラットフォーム、(2)地域研究教育連携推進機構、(3)都市部大学と地方(大学・地方公共団体)との連携、(4)その他地域アクセス確保。次回は7月31日の予定。