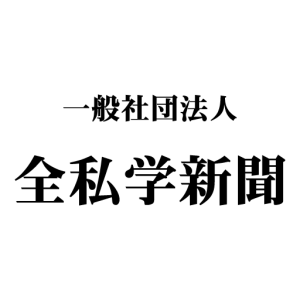全専各連等が理事会開催

第三者評価義務化の時期今後の焦点に
全国専修学校各種学校総連合会(会長=多忠貴・日本電子専門学校理事長)の第140回理事会と全国専門学校協会(多忠貴会長)の理事会の合同会議が2月27日、東京・市ヶ谷の私学会館で開かれ、それぞれ令和7年度の事業計画原案と収支予算原案が審議され、承認された。両団体がそれぞれ今年6月に開催する定例総会で令和7年度の事業計画案、同収支予算案として審議される予定。
この日は議案の審議に先立ち、文部科学省の米原泰裕・専修学校教育振興室長が、「専修学校をめぐる最近の動向について」と題して行政報告を行い、令和7年度の専修学校関係予算案の概要や、昨年の通常国会で成立した「学校教育法の一部を改正する法律」の施行(令和8年4月1日)に伴い、大学と同等の項目での自己点検評価の義務付けや外部の識見を有する者による評価(第三者評価)の努力義務化が課されるが、大学院入学資格を得られる専攻科の設置も可能となり、大学の学部と同水準の教育の質保証が求められることや、国際的通用性の確保等から、特別な教育課程や取り組みに対して認定を行っている場合は、優先的に第三者評価を求めていくことにしており、米原室長からは、まず大学院入学資格が付与される適格専攻科、同様に大学院入学資格が付与されている4年制以上の専門課程、また外国人留学生キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定)認定校について第三者評価を義務付けること、次の段階では職業実践専門課程(文科大臣認定)に広げることなどを検討していること、第三者評価を受ける期間については5年に一度を考えており、令和8年度から義務化された場合でも実施までに4、5年、あるいは5、6年の準備の期間があることなどを説明した。
しかし全専各連・全専協では早くも外部評価の義務化の動きが出ていることに、「唐突感が否めない」としており、義務化の対象範囲と開始時期の設定に当たっては、各認定校数や準備期間に十分配慮した上で、全専各連と文科省との合意形成が必要であり、その際、「評価の質の担保・評価者の確保」、「評価の受審に伴う負担やインセンティブ」等や、専門学校の地域性、規模の違いによる諸課題について考慮すべきだとの見解をこれまでに同省に伝えている。
理事会での米原室長の説明に対して、多会長は適格専攻科、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(188校)に関しては令和8年度からの義務化に一定の理解を示したが、認定校数が比較的多い(342校)既存の高度専門士(大学院入学資格付与)課程については開始時期をずらす、経過措置を設ける必要性、職業実践専門課程の認定校(1110校)については高度専門士課程の実施の目途が立った後に適切な時期の実施を要請した。米原室長は「専門学校の評価は大学とは異なり向上に重点がある。費用対効果を考え、できるだけ絞り込んで進め、評価の柔軟性も高めたい。3月中には結論を出したい」と語った。全専各連の令和7年度事業計画案では今年7月に「専修学校制度制定50周年記念式典」等を開催することにしている。