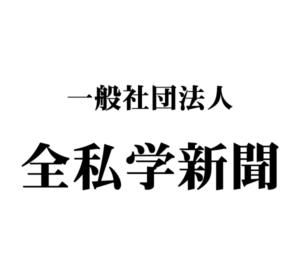第1回教師を取り巻く環境整備特別部会開催
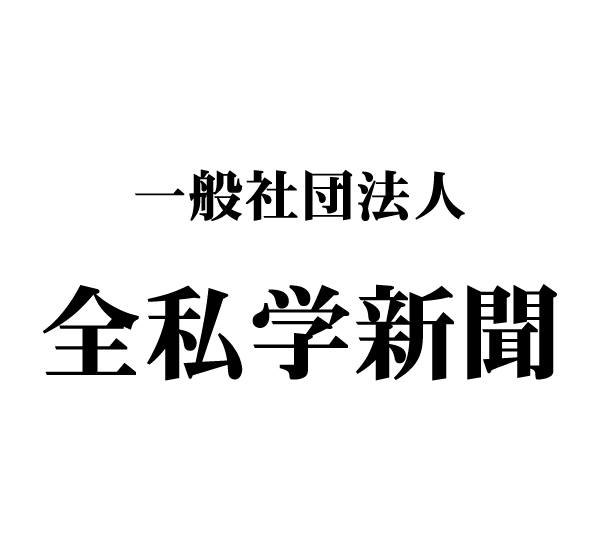
今年6月の給特法改正受けて
業務量管理・健康確保措置実効性向上措置を検討
文部科学省中央教育審議会初等中等教育分科会は7月9日に第1回「教師を取り巻く環境整備特別部会」を文部科学省でオンラインを併用して開催した。「質の高い教師の確保特別部会」から改称した同特別部会は、今年6月に成立した給特法改正を教師の働き方改革を推進する法律として見直し、教師を取り巻く環境整備を進めるための方策を審議する。具体的には給特法の施行(令和8年4月1日、教員の処遇の改善は令和8年1月1日)に向けて、「教育委員会が教員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(以下、指針)の改訂など、全ての教育委員会の改革の実効性を向上させるための方策が審議される。部会長には貞広斎子・千葉大学副学長が選任された。文科省は指針の改訂案を作成し、その概要を説明した。改訂案では第2章に、学校業務の適正化のために、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定の項を新設し、服務監督教育委員会が構ずべき業務量管理・健康確保措置の項を拡充する。実施計画では、時間外在校等時間の目標は、現在実現できていない、全ての教員が1カ月の時間外在校等時間45時間以下を目指すこと、1年間の1カ月時間外在校等時間を平均30時間程度とすること、とする。
時間外在校等時間の目標以外にも働きがい、ワーク・ライフ・バランスに関する目標を自治体の実情に応じて設定する。
業務量管理・健康確保措置の内容は、学校・教師の業務の役割分担の見直しを徹底するために「学校・教師が担う業務に係る3分類」(3分類)にある、「基本的には、学校以外が担うべき業務」を「学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要がない業務」を「学校の業務だが、教師以外の担い手の積極的な参画を促すべき業務」と変えることを提案。また現行の3分類に基づく14業務は、今日の状況を踏まえて、以下の視点から内容をアップデートすることも提案。
▽教師の勤務時間より前や下校時刻以降に児童を預かることは本来の学校の役割とは異なり、放課後の児童の居場所づくりは、地域、保護者が担うなど役割分担を明確化。▽保護者などからの過剰な苦情や不当な要求は、中教審答申で、行政責任で対応する必要性が示されている。▽教員業務支援員などの支援スタッフの配置拡充が進み、学校教育法施行規則にそれらの職が位置付けられた。▽GIGAスクール構想で校務DXの活用が進んでいる。▽高校で行われている業務や、副校長・教頭の負担軽減につながる業務も3分類に加える検討の必要がある。
そのほか保護者や地域住民の理解や協力を得ることが重要で、教育委員会は学校運営協議会の設置、活用を推進し、首長と連携し、保護者や地域住民に協力依頼をする。
校長などの管理職の人事評価の評価項目や研修内容に働き方改革のための組織マネジメントに関する内容を加える。
教師の服務を監督する教育委員会の責務は重要であり、果たすべき役割を指針に具体的に示す。
同省の説明後、特別部会委員に意見求められた。人材確保に関しては、「支援が必要な児童生徒には福祉の関わりが必要で、学校以外の主体が行うべきこと。人材確保のための国費の措置が必要だが、モデル事業を行い、どれだけ財源が必要か検討したい」「事務職員は多くの学校で配置は1人だけ。支援スタッフの拡充が必要」などの意見が出された。また、「中学校教師の時間外在校等時間を減らす際にネックとなるのは部活の指導。地域で支援者を見つけるのは難しい。財源支援が必要」「地域の立場から見ると、業務を地域住民やボランティアに委ねると責任問題が生じかねない。学校と地域の双方が課題解決に協力し合うことが大切」など地域の支援の課題が提起された。
高校の業務に関しては、「3分類に高校ならではの業務を入れてほしい。高体連の運営などは外部に任せたい」、管理職のマネジメントには「管理職はリスクを恐れず、学校でやらなくていい業務はしないよう進めてほしい。働き方改革に関してボトムアップはあり得ない。そして管理職のリーダーシップを評価できるようにしたい」「時間外在校等時間を減らすには管理職のマネジメントが重要だが、あまりマネジメントを強調すると管理職のなり手がいなくなるのが心配。国や教育委員会の伴走支援が必要」などの意見があった。