中教審第11回教育課程特別部会開く
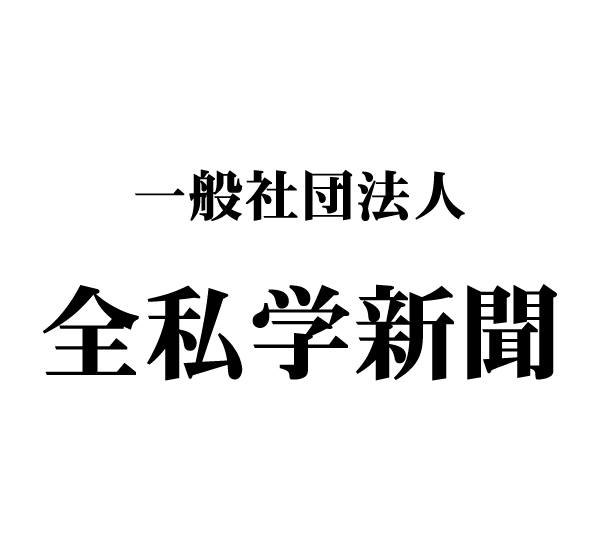
高校の柔軟な教育課程など議論
高校入学者選抜の見直しも
文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会の教育課程企画特別部会(主査=貞広斎子・千葉大学副学長)は7月28日に同省で第11回特別部会をオンラインも併用して開催した。
この日の議題は、高校の柔軟な教育課程、産業教育の更なる改善、中学高校の円滑な接続に資する高校入学者選抜等。
生徒の多様性が高まり、地域や高校ならではの特色を模索する必要が出てきていて、地域の教育資源を生かした授業を行うなど特色ある教育課程を持つ高校が生まれつつある。しかし、基礎科目を履修しないと発展科目が履修できない仕組み、学習内容の習熟の早い生徒、遅い生徒を受け止める教育課程編成がしにくいことなどが柔軟な教育課程の妨げになっている。そこで文科省は具体的な次のような改善策を提示した。
(1)必履修を含む科目の履修の一部、または全部を、一定の要件をつけて、同一教科の他科目や学校設定科目などで取り扱えるようにする。
(2)現行の卒業に必要な単位数74単位を半期ごとに分割、148単位とし、学期ごとの単位認定を可能にし、きめ細かく増単、減単できるようにする。
(3)例えば英検などの外部試験で高度な外国語の能力を持っていると判断された場合には、一定の要件の下、当該教科・科目の履修を免除できる仕組みをつくる。
(4)柔軟な教育課程を進められるようにしつつ、大学入試対策に傾倒するなど不適切な運用を防ぐ取り組みを考える。
(1)から(3)の仕組みを取り入れながら、全日制、定時制、通信制の相互乗り入れ、学年による教育課程の区分を設けない単位制高校への移行、高校間での単位互換や地域留学、産業界と連携したカリキュラム開発、高等教育機関と連携した単位認定などをしやすくする。
さらに農業科、工業科などの専門高校に関しては、産業界の実情を踏まえ、市場環境の急激な変化や業態変更に柔軟に対応する力を育成するために、産業教育に共通する資質・能力を検討、各教科共通に学習指導要領に記述すること、データサイエンスやAIを活用した実践的な学びを充実させること。各専門科目で身に付けるべき資質能力を明確にする、といった改善イメージが提示された。
高校入学者選抜については、学力検査は思考力・判断力・表現力等を問う出題を推進する。不登校生徒に対する特別の教育課程に基づく評定、障害のある生徒の合理的配慮の提供など、生徒の特性を踏まえた入試方法を充実させる。このようなことを踏まえ、学力検査を行わない入試、調査書を用いない入試方法なども検討する。
文科省の説明を受けて高島峻輔委員(芦屋市長)から、公立高校入試改革への提案があり、入試は偏差値ではなく、高校の特色や魅力に応じたマッチングが重視されるべきと述べた。現状の内申点は毎日学校に通える生徒が前提の制度であり、不登校生徒など多様な生徒たちを評定するには配慮が必要で、生徒の主体的な日常の行動を評価する内申点制度に変える必要があると指摘。また授業が探究的内容に改良されているので、入試問題も探究的な出題が求められる。良質な記述式・探究的な問題を出題するために、都道府県を超えた、作問の協働を検討したい、との発言があった。文科省から高校の教育課程の改善の他に、子供が主体的に社会参画するための教育の改善、カリキュラム・マネジメントの在り方も課題として挙げられた。
委員による論議では、教育課程の改善で、74単位を半期ごとに分割し、148単位とする案には、教師の裁量を広げる、余白を作り出せると賛同の意見が多く出された。
一方、「思考力・判断力・表現力を育てる教育に転換を図っている状況で、習熟している教科・科目の履修を免除するのは危険。習熟度をどう判断するのか」と履修免除には熟考を求める発言があった。また「多様性の尊重は大切だが、今、高校生は二極化しており、義務教育の内容が理解できていない生徒もいる。それができていれば自分で学習していくので、自走する学び手を育てることが重要」という意見も聞かれた。


