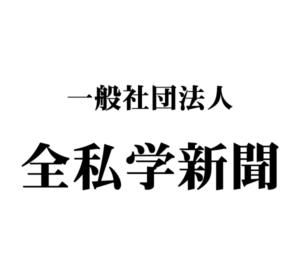中教審第3回質向上・質保証システム部会

生成AIの利用、ミネルバ大学の改革などを聴取
大学の質向上策を審議
中央教育審議会大学分科会の質向上・質保証システム部会(部会長=伊藤公平・慶應義塾長)は7月14日、文部科学省でオンラインも併用して第3回部会を開き、今後の大学教育の質に関わるAI(人工知能)の利用の可能性やAIによる高等教育の変容の展望、またキャンパスを持たず世界の7都市に滞在し寮生活を続けながらオンラインで少人数アクティブラーニングやインターンシップ等を行う、ミネルバ大学(本部=米国・サンフランシスコ)が育成を目指すHCs(汎用的/分野横断的能力)について専門家から現状や課題等を聴取、その後、発表者を交え同部会の委員間で意見交換を行った。
AIに関しては、初めに吉田塁・東京大学大学院工学系研究科准教授が「生成AIと教育における活用可能性」と題して発表を行い、その中でリアルタイムで既存のAIサービスを活用して、AIと特定のテーマについて自然な話し合いや、吉田氏の日本語で話す動画を英語の動画に即座に変換(英語を話しているような口の動きを再現)するなど生成AIの現状の能力等を披露。またAIの性能は年々向上し、学習者向け活用例としては、個別学習支援(相談相手としてのコメント・フィードバック作成等)、グループ学習支援(ファシリテーター等)、課外活動支援(学園祭運営支援)等があり、また教職員に対する支援では授業支援(授業案作成、評価補助等)校務・事務支援(報告書作成補助等)、研究支援(英訳等)等があること等を説明した。
その上でAIの出力を鵜呑みにせず、最終的に使用する人が判断することが重要で、簡単な問題でもAIは間違うこと(hallucination)があり、またバイアス・毒性が存在すること、機密情報の流出の可能性があること、過度な依存を促す可能性がある等の課題を挙げた。
しかし今や小学校でも活用(例えば生成AIが秋をテーマに出力した俳句を批判的に検討した後、小学生が俳句を作成、最後に画像生成AIを用いて挿絵を出力するなど)が進んでいることを紹介、活用に際しては、生成AI(ChatGPT)の使い方により演習とテスト成績への影響が異なることなどからAIの賢い使い方が重要で、思考の丸投げは注意が必要で、実際に利用して試行錯誤することが大事であり、手段が目的化しないよう注意を促した。
続いて飯吉透・京都大学学術情報メディアセンター教授が、「生成AIによる高等教育の変容を展望する」と題して発表を行った。その中で生成AIは、(他のAI技術共々)ごく近い将来「大した技術」となることは明白で、職業や働き方の変容を伴った大きな社会変革を引き起こし、教育機関としての大学や高等教育システム全体を大きく変容していくとし、「汎用的な知的能力」を習得させることを、より重視しつつある現行の大学教育は(生成AIから)深刻な挑戦を受けている、と指摘。ただ近年世界の高等教育の潮流に乗り遅れた感のある日本の大学界がAIや自動翻訳ツールなどのスマート・テクノロジーを使うことで巻き返しを図れる大きなチャンスが到来することもあり得るとして、現在の生成AIを巡る様々な動きや議論を通じて、今の高等教育の課題や可能性について詳細・広範に考察・洞察することが重要だ、と提言した。
ミネルバ大学に関しては、同システム部会の委員の松下佳代・京都大学大学院教育学研究科教授が、「ミネルバ大学のイノベーション―汎用的能力の育成を中心に―」と題して発表した。その中で汎用的能力については、分野や場面を問わず、広い適用性を持つ能力のことで、批判的思考、創造的思考などが代表的なもので、20世紀末頃から教育政策の目標とされていることなどを説明。2012年に設立されたミネルバ大学については、世界で最もイノベーティブな大学とされており、大学が卒業後の社会や生活に対して準備ができた状態にまで学生を育てられていないことや、大学教育があまりに高額になり、ほとんどの学生が負債を抱えて卒業していることなどの問題を解決し、世界のリーダーを育成するため意図的にゼロから立ち上げた大学で、1年次の一般教育では4つのコア・コンピテンシーと約80のHCsを学び、2年次からの専門教育は5専攻に分かれ(ダブルメジャー、メジャー・マイナーを推奨)、専門分野の知識・スキル(LOs)を学びながら、並行してHCsを使い、3・4年次の“卒論”では両者の統合を図る、などと説明。同大学は問題点はあるが、常識を問い直して大学を構成する要素を見直し、テクノロジーの力を最大限活用して「新結合」を創り上げた、と評価。日本の大学についても大学教育の常識を問い直して自分たちならではの新結合を生み出す重要性を指摘した。
こうした専門家からの発表に対して、同部会委員からは、大学全体で生成AIを活用するには大変な資金がかかることや、業者選定も難しいことなどが指摘され、吉田氏は「無料版から始めるのが良い。無料版でもかなりのことができる。(入力した情報を)学習されない生成AIもある」と回答。またミネルバ大学が安価な学費(日本の国立大学並み)で運営している資金面の背景等を尋ねる意見も聞かれた。