科学技術・学術審第4回次世代人材育成WG開く
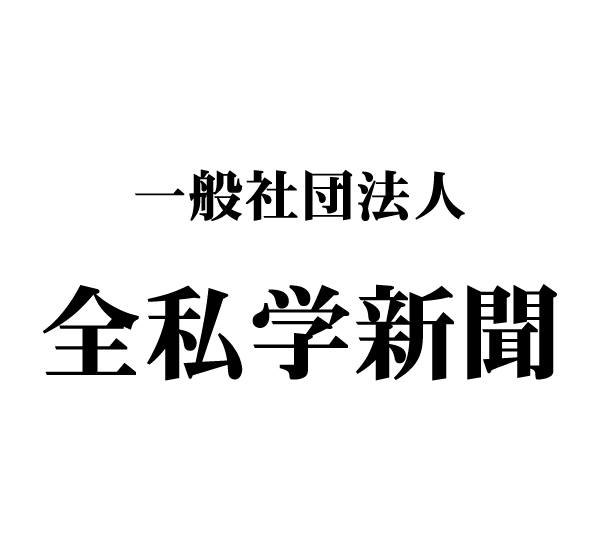
審議の中間的まとめ了承
人材委員会が「中間まとめ」策定へ
文部科学省科学技術・学術審議会人材委員会は6月28日、同省内でオンラインも併用して第4回次世代人材育成ワーキング・グループ(主査=狩野光伸・岡山大学副学長)を開催し、(1)博士後期課程学生支援、(2)初等中等教育段階での科学技術人材の育成、(3)科学技術コミュニケーションのそれぞれ現状・課題・今後の具体的取り組みを提言した審議の中間的まとめ案について検討し了承した。最終的な修文は狩野主査に一任となった。
また別の科学技術人材多様化WGで審議してきた内容等を盛り込み作成された「今後の科学技術人材政策の方向性(中間まとめ概要)案」も審議し、了承した。これらの審議内容は7月30日に開かれる人材委員会で「中間まとめ」として取りまとめられる見通し。
次世代人材育成に関しては前述の(1)、(2)、(3)が中心的な検討課題。
このうち博士後期課程学生への今後の支援事業では、SPRING(次世代研究者挑戦的研究プログラム)での日本人学生に関しては、研究奨励費(生活費相当額)を支援、研究費については申請者の要望や研究実績等に基づいて支給額を階層化・差位化すること、留学生に関しては研究奨励費の支援は行わず、個人の研究活動に係る研究費を支援すること、社会人学生については研究費を支援、支給額は階層化・差位化する方針。
また特別研究員(DC)制度に関しては、主にアカデミアで活躍する優秀な研究者を育成する事業として、研究奨励金(月額20万円)の単価増等を検討・実施すること、DCとして認められた研究計画に基づく活動が着実に進んでいることを確認するなど一定の条件下で研究成果を基にした起業を認めるよう、制度的見直しを行う、としている。
また初等中等教育段階では、次世代科学技術チャレンジプログラム(STELLA)の実施拠点数を拡充、研究成果の発表や交流機会等の充実・確保を進める。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業については、全国の高校の約5%に相当する250校という目標の達成に向け、指定校を拡充、SSH指定校の中に事業の中で目指す人材育成戦略等に応じた類型を設け、類型に応じて支援金額にも差を設けることを検討するなど事業設計の改善・見直しを実施する。また将来の科学技術人材育成に意欲的に取り組む指定校の取り組みを一層強化・発展させるための支援を強化する。
発展Ⅰ期・Ⅱ期での類型設定に関しては、(1)社会で活躍する高度科学技術人材育成を目指す指定校、(2)科学的な探究活動を高度に遂行できる人材の育成に特に重点を置く指定校、(3)国際感覚に優れた高度科学技術人材の育成に積極的に取り組むと同時にSSHとしてのリーディングな取り組みに挑戦する指定校の3類型とし、(1)では「理数探究基礎」「理数探究」等の科学的な探究活動を、全校生徒を対象に3年間設定すること等、(2)では大学や企業等との共同研究の実施や発展的な内容を扱う理数系科目の開設等、(3)では国際共同研究の積極的な実施、国際会議・大会への参加等といった取り組みが想定されている。
一部の類型については前期の中間評価で一定以上の評価を得ること等、申請に当たって要件を設けることも検討する。人材委員会の「中間まとめ」公表後、詳細な制度設計はスーパーサイエンスハイスクール企画評価会議で検討、令和9年度から見直しを本格的に実施する計画だが、令和8年度に一部事例を作る方針。
こうした先進的な理数系教育の充実・強化に関しては、中間まとめの注釈として、「ここで言う理数系教育には単に理数系の教科・科目に関する知識・技能の習得のみならず、いわゆる文系の教科・科目に関する知識・技能とも組み合わせながら自分なりの問いを立て、立証し発信していくという探究力・表現力を育成することも含まれる」が追記される。
(3)に関しては、倫理的・法制度的・社会的課題(ELSI)も含めた、次代に即した科学技術コミュニケーションの推進が極めて重要だと指摘、科学技術に関わる政策に関する市民、産学の科学技術人材、政府関係者等の対話の促進、多様な科学技術コミュニケーション能力が適切に評価されるような仕組みの検討・推進等を提言している。


