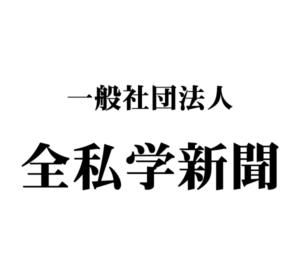私学振興協議会を開催

自由民主党議員と私学団体代表
私学を取り巻く課題協議要望
遠藤利明・衆議院議員と全私学連合の田中愛治代表(早稲田大学総長)が共同代表を務める「私学振興協議会」が6月16日、都内のホテルで開かれ、国の私学振興予算や税制改正など私学を取り巻く諸課題について意見交換が行われた。会議には文部科学(文部)大臣や文部科学部会長経験のある自由民主党議員(遠藤利明、今枝宗一郎、木原稔、柴山昌彦、末松信介、渡海紀三朗、永岡桂子、中曽根弘文、中村裕之、丹羽秀樹、松野博一、山田賢司の各議員)が出席、私学側からは全私学連合を構成する私学5団体の会長等6人が出席した。
2人の共同代表があいさつ、その後、現在の自由民主党文部科学部会長の今枝宗一郎氏があいさつし、その後、私学団体側から、私学が直面している課題についての説明と要請が行われた。
初めに日本私立大学団体連合会(略称:私大団体連)の田中愛治会長が、同連合会を構成する2団体の一つ、日本私立大学連盟の会長の立場から、わが国の学生の8割の教育を担う私立大学がどれだけ質の向上が図れるかが、国民全体の能力の総和の増減に大きく関わることを説明、質の向上のため、(1)私立大学経常費補助における「機能別」支援の強化、(2)私立大学の教育研究力の飛躍的向上に向けた施設・設備費の抜本的拡充、(3)数理・データサイエンス教育の他、高度な文理横断教育を進める人文社会系への支援、(4)大学の高度化を目指し学部の収容定員を減員し大学院へシフトする大学、学部の規模を縮小する大学等への支援を要望した。
また要望を裏付けるデータとして、政府が目下最も重要視する理工農系分野の学部で学ぶ学生の61%を私立大学が育成していること(国立は全体の33%、公立は6%)、大学別の大学発ベンチャー数の上位10校の中には慶應義塾大学(2位)、東京理科大学(7位)、早稲田大学(8位)、立命館大学(10位)の4校が入っていること、施設設備整備への国の補助は、学生1人当たりに換算すると私立大学は約9千円、国立大学は約20万円でその格差は22・7倍もあること、理工農系分野には基金(3002億円)による大規模かつ継続的な支援が行われているが、文理横断教育に対する私立大学への支援は限定的であり、事務系社会人はエビデンスベースで話す力が弱く、人文社会系はもっと国際競争力を付ける必要性を強調した。
また私大団体連のもう一つの構成団体・日本私立大学協会の小原芳明会長(玉川大学理事長・学園長)は、全国に立地する私立大学(学生数の約80%を担う)が多様な学問分野における教育研究の質的充実と特色化・高度化、「総合知」を活用した教育の実践で、わが国の将来を担う多様な人材の育成が重要であること、そのためには私立大学に対して、国・地方公共団体による公財政支援の拡充と個人等からの寄附による支援の強化(寄附税制の改善)が不可欠であることを強調。
具体的には政府が進める政策「地方創生2・0」実現の観点からも、国による支援の充実と併せて地方公共団体による安定的・継続的な支援措置の必要性を指摘。また特定分野の高度専門人材の育成と同時に、文理横断教育、数理・データサイエンス・AI教育、アントレプレナーシップ教育等の推進で人文社会系を含めた全ての分野において、昨今の物価高騰等に係る負担等を加味した上での支援充実策が講じられるべきだと語った。
また国策の実現に資する私立大学の取り組みへの寄附に係る「税額控除」の控除率の引き上げ(現行40%、最大100%まで拡充を要望)を求めた。
国策の実現に資する取り組みとは、成長分野をけん引する人材育成(理工農系等、リカレント教育)、少子化対策(教育費負担軽減=授業料減免支援)、グローバル化の推進(留学生の派遣・受け入れ)、防災・減災・国土強靭化(耐震化等防災機能強化)、脱炭素社会の実現(省エネ対策)等。
日本私立短期大学協会の麻生隆史会長(山口短期大学理事長・学長)は私立短期大学が直面している課題を説明。その中で昨今の人口減少や社会構造の変化により、多数の私立短期大学が学校存続、地域や地方を支えるエッセンシャル・ワーカー等の輩出が困難になってきていることを説明。短期大学士の学位を保持した専門的職業人材を持続的に育成・輩出するための支援の強化、法令で定められた認証評価機関による適格認定を受けているにもかかわらず、修学支援制度で機関要件を満たしていないとされる制度の抜本的な改正、一定の基準を満たす短期大学の専攻科については、修了者に大学院入学資格を付与するなどの制度改正を要望した。
日本私立中学高等学校連合会の吉田晋会長(富士見丘中学高等学校理事長・校長)は検討が続いている「いわゆる高校無償化」に関して、その実施に当たっては、学校の代理受領で円滑に進められること、合理的な理由による授業料の改訂、経常費助成による継続的な支援、専門高校を含む公私の役割分担を要望。
また私立高等学校等経常費助成費等補助の大幅な拡充強化(一般補助)と同特別補助の拡充強化、私立中学校等についても国として中学校等就学支援制度の創設、ICT環境整備補助の拡充強化、施設の耐震化・高機能化に関する補助の補助率の引き上げ、国公私の別なく全額の公費負担、物価高騰に対応した国内研修・修学旅行等への支援強化、日本私学教育研究所等への補助拡充等を要望した。
日本私立小学校連合会の斎藤滋会長(桐光学園小学校校長)は、入学者の多様化が進み、個別支援が必要な児童が増えていること、ある私立小学校で個別支援が必要な児童が昨年の18人から今年は40人に増えるなどしていることなどを説明して、公私間格差の是正策として、私立小学校での特別支援教育への教員加配・採用、特別教室の設置等に対する支援制度の新設、公立小学校での給食費相当額を保護者負担軽減の立場から補助、ICT環境整備での公立と同等の公的支援措置等を要望した。
全日本私立幼稚園連合会の尾上正史会長(紅葉幼稚園理事長・園長)は幼児教育振興法の制定を要請したほか、人手不足の中で幼稚園教諭等を紹介する業者が高額の手数料を徴取していることを問題視、行政による指導の必要性を指摘。また私学助成拡充等を要望した。
こうした私学側からの要請等に対して国会議員からは、「短大+専攻科で大学院入学資格取得をぜひ実現したい」といった意見や、公立学校の給特法が改正され、教職調整額を10%まで徐々持っていくが、私学ではどう働き方改革に取り組んでいくか大きな課題」「子供に着目した支援は出しやすいが、学校に着目した支援は難しい」などの意見が出された。
最後に遠藤共同代表は、部活動の強豪校が多い私立学校の働き方改革をどうしていくのか、通信制高校やインターナショナルスクールが増加している問題、大学・大学院の修業年限の問題も丁寧に議論していきたい、などと語った。