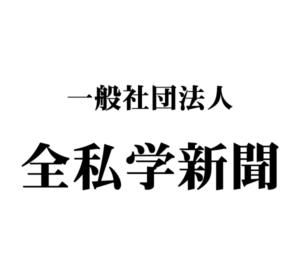第3回社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議

私立大の国際競争力強化策など検討
特筆すべき研究成果の私大に国立と同一の投資など要請
中央教育審議会の今年2月21日のいわゆる「知の総和向上答申」を受けて、これからの私立大学の在り方等を審議している文部科学省の「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」(座長=小路明善・アサヒグループホールディングス株式会社会長)は6月18日に都内で第3回会議をオンラインも併用して開催した。
会議前半は、(1)国際競争力の強化に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方に関して、文科省から関連データや現行制度等が説明された後、伊藤公平委員(慶應義塾塾長)、石川正俊委員(東京理科大学学長)、村上元芝浦工業大学学長の3人から意見発表が行われた。
この中で文科省からは世界大学ランキング2024に、世界に約3万1千校ある大学の中から1904校(6・1%)のみ掲載され、日本の大学からは119校がランクイン(米国に次いで2番目に多い数)、その119校には私立大学が約50校入るなど、質の高い私立大学の層は厚いこと、文科省の機能強化基金等により理系分野への転換も急速に進んでおり(2023年度、2024年で私立大学109校が転換)、大学発ベンチャー企業の立ち上げ数トップ10大学(2024年度)には私立大学が4校入り、増加率(2023年度比)ではトップ10中、5校が私立大学となっているが、国立大学と比べ同程度の国の科学研究費助成を獲得している私大でも国による基盤的経費に対する支援額は国立大学と比べ非常に少ない状況にあることなどが説明された。
また伊藤委員は、国から約565億円の運営費交付金を受けている京都大学と88億円の経常費補助金を受けている慶應義塾大学は同程度の世界的に影響力のある研究者を擁していることなどを指摘。その上で特筆すべき研究成果を上げている私立大学に対しては、国立・私立といった設置形態にかかわらず、国立と同一な設備投資や特別補助、研究者へのインセンティブを提供してほしいと要請。石川委員は、私立大学(東京理科大学)は国立大学(東京大学)と比べ投資効果が高いこと、国立大学でも収益事業ができるようになるなど、私立大学との事業形態に差がなくなった中で、私立大学に対する制約は今や意味がないことを指摘、その具体例として、高額給与教員を雇用すると経常費補助金が減る、国立大学で土地等の貸し付けが非課税で可能になったのに私立大学では同類型の事業が課税対象、大学債発行の手続きが極めて煩雑、大学キャンパス開発に関する要件が厳格なこと等を列挙した。また特に研究重点型私立大学で、国際競争力、専門人材の養成を期待する大学に対しては、現状の問題点を緩和した効果的な支援や日本の私立大学型のモデル構築が必要なことを強調した。
さらに村上元学長は、研究力向上にための有用な国の支援に関して、大学院生への支援、JASSOでの奨学金返還全額あるいは半額免除、科研費等の競争的資金は広く浅くなどを求めた。
続いて石川正俊、伊藤公平、鶴衛(学校法人鶴学園理事長・総長)、日色保(ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社代表取締役社長)の4委員がこの日の議題に関して論点等を整理した「検討課題」が小路座長から報告された。同検討課題は国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化や日本の産業を支える理工農系人材の育成に関して今後検討すべき具体的な施策等を挙げたもの。
その後、委員による意見交換等が行われ、委員からは「産業界から専門人材に(大学へ)来てほしい。教員審査のあり方を見直してほしい」「小さな科研費事業でも事務処理が大変。100万円の科研費を10件獲得するのと1000万円を1件獲得するのでは10倍手間が違う。手間への支援(間接経費をここまで払うという下限)を考えてほしい」「国私間の不均衡、制度的制約を考えていくべきだ。学校法人の経営者には研究者への理解に向けた意識改革が必要」などの意見が出された。
会議後半では日本の産業を支える理工農系人材の育成について審議された。初めに文科省から理工農系人材の育成の現状、理工農系分野への財政支援が報告され、続いて経済産業省から2040年の就業構造推計や、「科学とビジネスの近接化」時代のイノベーション政策と大学とのテーマで報告が行われた。
将来の産業構造としては、製造業がGX、フロンティア技術で差別化、DXによるサービス化等で新需要創出による高付加価値化により雇用拡大・賃上げを実現し、国内に残ること。情報通信業・専門サービス業は、新需要開拓で新たな付加価値を創出、他産業を上回る賃上げを実現すること。介護・社会福祉、医療、小売業、建設業等は、省力化設備・サービスを使いこなして賃上げを実現、アドバンスト・エッセンシャルサービス業となることなどを説明。また経産省として産業界との共同研究の大型化、大学発スタートアップ、知的財産等、多様な手段による財政基盤づくりに支援していく考えを明らかにした。
その後、鶴委員が地方私立理工系大学が地域産業の人材供給源となっているが、大型装置等の取得に苦労していることなどを報告。名城大学の小原章裕・専務理事は奨学金制度を拡充したことで農学分野の修士学生が8年で2・9倍となったことなどの現況を報告、国の支援増を要請した。次回検討会議は7月28日。
委員等が千葉工業大、早稲田大を視察
同検討会議は第3回会議までに千葉工業大学、早稲田大学に視察に出向いている。
千葉工業大学には5月29日に6人の委員が訪問したが、文部科学省から浅野敦行・高等教育局私学部長、森友浩史審議官等が、また経済産業省からは産業人材課長等、総務省からは地域力創造グループ地域政策課の担当官が参加した。
千葉工大からは教育に対する取り組みが説明されたほか、国際競争の中での研究力の強化などが説明された後、惑星探査研究センターや未来ロボット研究センター等を見て回り、社会実装に取り組んできた実績や修士課程の学生と意見交換した。学生からは文系と比べ授業料が高いことの不安が入学前にあったが、生涯年収が高いことも考え頑張っていることなどが語られた。
6月11日には早稲田大学を9人の委員が訪問。国際競争力の強化に資する先端研究、大学の垣根を越えたデータ活用人材育成、地域探究・貢献入試や北九州キャンパスを活用した地域貢献の取り組み、業務の戦略的アウトソーシングや全国の大学への展開、オフィス運営への学生スタッフの参画等について概要の説明を受け、施設を見て回った。早稲田ポータルオフィスの学生スタッフとして働く学生との意見交換も行われた。