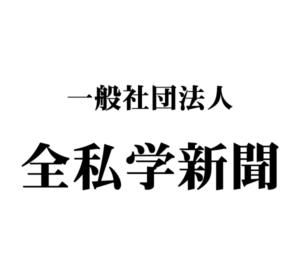第3回新たな評価の在り方ワーキンググループ
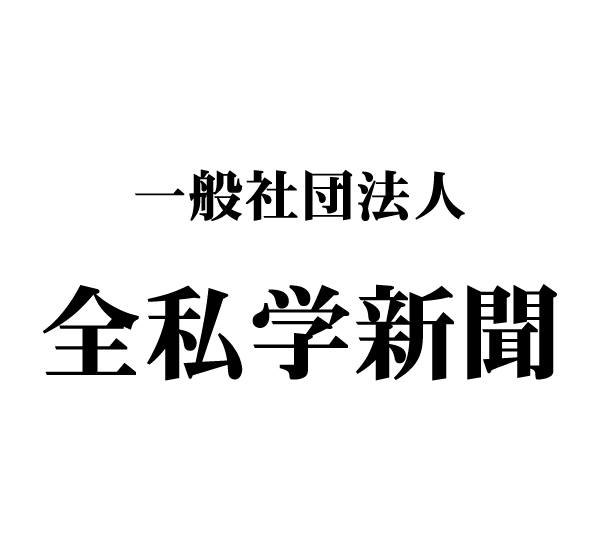
新たな評価制度への期待など
大学、短大団体等から聴取
中央教育審議会大学分科会の質向上・質保証システム部会の下に設置されている「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」(主査=森朋子・桐蔭横浜大学長、以下WGと表記)は6月10日、文部科学省でオンラインを併用して第3回WGを開催した。前回は大学基準協会など認証評価機関からヒアリングを行ったが、今回は評価を受ける大学等の団体等から現在の認証評価の課題や今年2月の中教審答申で提言された新たな評価制度についての期待等を聴取した。
同WGは、今年2月の中教審「知の総和向上」答申の提言に沿って、教育研究の質の更なる高度化のため大学等の認証評価制度を再検討するのが目的。中教審答申では、現在の大学の教育研究等の総合的な状況(機関別評価)が評価基準に適合しているか否かから、対象を学部・研究科等にして学生が在学中にどのくらい力を伸ばすことができたのか等を含め教育の質を数段階で評価する新しい評価制度に移行することなどを提言した。
第3回WGでは、まず機関別認証評価(7年以内に一度)を受ける大学、短期大学、高専が組織する国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学連盟、日本私立大学協会、全国公立短期大学協会、日本私立短期大学協会、国立高等専門学校機構から現状認識と新評価制度への期待等を聴取、続いて分野別別認証評価(5年以内に一度)を受けている法科大学院で組織する法科大学院協会、専門職大学の集まりである専門職大学コンソーシアム、最後に同WGの中村真理子委員(東京慈恵会医科大学教育センター長)から医学教育評価の現状や課題、今後について聴取した。
この中で、国大協は認証評価の現状について、「評価する側とされる側、共に負担感が大きく、基準を満たしているかどうかの形式的な評価対応で、事後的なチェックとしてはうまく機能していないのではないか」とし、教育の質を数段階で示すことに関しては、「大学や学部・研究科ごとに理念や3つのポリシーが異なる中で、同じ基準で教育の質を比較する標準化された仕組みは現在日本にはないと思われる。国民に対して誤解を招くことが無いような段階評価となることと、評価結果に納得感のある評価の仕組みに期待」と述べた。
また私大連はWGの照会に対して加盟大学から寄せられた意見を紹介したが、新評価制度への期待では、「適合した大学を数段階に分けて示すことは非常に重要。高校、受験業界、産業界、マスコミなどから大きく注目を集め、各大学の努力が報われる」とする意見、また留意点に関しては、現行制度の検証の必要性、評価指標・評価基準の標準化や評価の数値化がもたらす教育・研究の画一化、一律化(多様性・自律性の喪失)等を指摘。
私大協は「教育に対して段階的に「優劣」を付け、「撤退」を促すことは、このピアレビューの精神に馴染まない。学部・研究科等に応じた定性的評価については拙速な導入は避け、慎重に検討することが望まれる、などと述べた。
日短協は、新たな評価制度への留意点に関しては、段階的評価の導入や質保証のあり方について慎重な議論が必要なこと、また教育機関の実態に即した評価制度設計への期待を表明した。
一方、分野別認証評価に関して、法科大学院協会は、法科大学院に対する新たな評価の論点については、法科大学院の枠組みの中で評価を実施すべきで、課題があると評価された場合には受審期間を短縮化、優れた場合には受審期間を延長する等、柔軟な受審期間を設定することの検討等を論点として示した。
専門職大学コンソーシアムは、専門職大学に期待される役割と教育の手法の特色に沿った評価項目と評価基準の設定、機関別認証と分野別認証を統合して数年に1回とするよう改善を要望した。
こうした意見発表に当たって、同WG委員からは、「国立と私立では人件費比率が大きく違うので、設置形態の違いに配慮してほしい」「撤退を促す評価制度の導入には反対」「ピアレビューの精神を忘れないでほしい」「JALも日産も厳しい経営状況でも政府は撤退に追い込まなかった。撤退に関しては自由経済の仕組みで各法人が判断すべきだ」「市場原理に任せていると、大規模校や学費の安い学校に学生が集中する」などといった意見が聞かれた。
次回・第4回WGは7月3日に開催。評価を活用する団体等からのヒアリング、海外の第三者評価の状況に関する委員からの報告が予定されている。同WGでは夏頃を目途に議論の経過を、質向上・質保証システム部会に報告する予定。