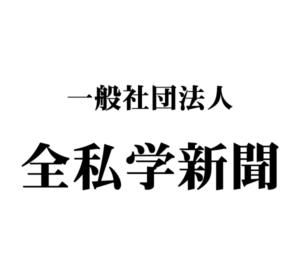第2回質向上・質保証システム部会
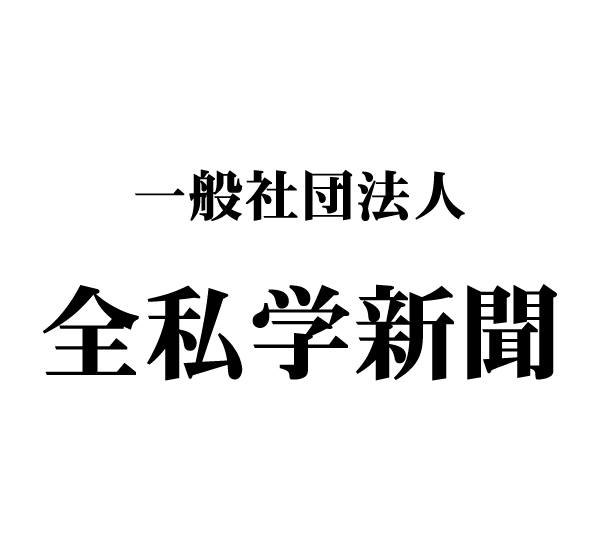
学士・修士5年一貫教育制度を議論
中等教育との連携強化の意見も
中央教育審議会大学分科会「質向上・質保証システム部会」(部会長=伊藤公平・慶應義塾長)は、5月26日、文部科学省でオンラインを併用して第2回部会を開いた。この日は、部会の論点の中から(1)学士・修士5年一貫教育制度と、(2)学生の主体的・自律的学習を支援するためのアカデミック・アドバイジングについて合わせて3大学から実践事例等を聴取し、議論を行った。
第2回部会では、初めに文部科学省から、4月23日開催の第183回大学分科会で委員から出された、新設する質向上・質保証システム部会への期待や注文等の意見が報告された。
その中で学士・修士5年一貫教育制度の在り方に関しては、「学部と大学院の関係性、4年制大学、短期大学、専門職大学、専門学校の制度的役割や接続関係、更には修士、博士の構造的整理に関わる。制度全体が複雑化している中で、その関係性を整えることが求められる」、「学部と大学院の接続を見直して、特に人文・社会科学系において、より多くの学部生が大学院へ進む魅力あるプログラムを担保する制度をつくることが重要」などの意見が出され、またアカデミック・アドバイジングに関しては、「これからの時代は一人一人が単に知識ということではなくて、知見を身につけて、自分の人生に生かしていくという環境づくりが必要。誰かに倣うのではなくて、自己思考力、自己決定力に結びついていくような教育が必要」などの意見が出された。
その後、論点(1)に関して、冒頭、伊藤部会長が発言し、「10代、20代にどれだけ学ぶ力を身につけ、志を醸成できるかが重要。しかし極端な少子化の中で企業の採用活動がますます勢いを増す中で、学生には自分達で考え選択し、世界を見ていく時間が必要。いかに学びの時間、経験の時間を与えることができるかが大事だ。5年一貫教育は効率的に学士、修士を取るためのものではなく、十分な時間を与えられるかということ」などと制度の意義を説明。
その上で同部会の松浦良充委員(学校法人慶應義塾常任理事)が慶應義塾で進めている学士・修士一貫制度/連携制度を説明した。例えば経済学部と経済学研究科での学部の早期卒業(3・5年)+修士早期修了(1・5年)の内部学士・修士5年プログラムや、看護医療学部・健康マネジメント研究科看護学専攻での5年一貫教育プログラム、総合政策学部、環境情報学部と政策・メディア研究科での学部・大学院修士4年一貫教育プログラムなど様々な5年一貫/連携制度等を紹介した。ただし法学部の法曹コースを除き、こうした制度が適用される学生は少数で、学生には高い学修意欲や優れた成績が求められるなど修了する難しさも説明した。課題、論点については、学士・修士の修業年限をどう配分するか、いわゆる「教養」と「専門」という枠組みをどう考えるか、入学者選抜の在り方、中等教育との接続、単位制度の抜本的見直し、学納金をどのように設定するか(1年分の「減収」をどう捉えるか)〈修了年限は短縮されるとしても、卒業・修了単位(教育・学修量)は同じ〉などを挙げた。
また松浦委員は、国際基督教大学や早稲田大学、帝京大学、武蔵野大学、一橋大学、九州大学、広島大学、神戸大学、東京大学でも実施あるいは実施を予定していることも紹介したが、同部会の委員からは「卒論(学部)、修士論文(大学院)がある大学では5年一貫はかなり難しいのではないか。教養教育にシワ寄せが来ないか」「大学入学時の最初から5年一貫プログラムを始める制度について議論する余地はあるか」「緩やかな大学の機能分化だ。高等教育同士の連携をどう考えているか」「自分の方向性について早い段階で見定めることができる学生は少ない」などの意見出された。
論点(2)のアカデミック・アドバイジングに関しては、初めに清水栄子・日本アカデミック・アドバイジング協会会長(愛媛大学教育・学生支援機構)が「アカデミック・アドバイジングの導入と制度化に向けた検討―米国との比較を手がかりに―」と題して、アカデミック・アドバイジング(以下、AAと表記)とは何か、米国・コロラド大学ボルダー校の制度と支援体制、日本においてAAが求められる状況、導入に当たっての4つの課題を説明した。AAとは履修・学修計画の助言、制度・手続きの案内、進路・キャリアの相談、学内リソースの紹介、継続的な対話と関係構築といったことで、わが国でも学生の多様化、カリキュラムの多様化、大学の研究力の低下、各種支援の連携不足、社会人の学び直しに対する参加率の低さ、大学の国際競争力の低下等からAAが求められているが、大学におけるAAの組織的な位置付け、アドバイザーの量的・質的な確保と育成、AAの国際通用性の確保、AAの制度的位置付けと政策的支援を課題に挙げた。
続いて新潟大学教育基盤機構教学マネジメント部門授業実施調整室長・未来教育推進コア分野横断教育ユニット長の上畠洋佑准教授が「新潟大学が挑戦する未来志向型アドバイジングモデル」と題して発表を行い、AAの課題については、認知度が低いことからAAの雇用・育成の難しさ、学生相談の複雑化(学修・学生生活・メンタル領域の混在)、大学内リソース不足(人員不足、資金面の不足)を指摘、その上で未来志向型のアドバイジングモデルについては、PM(ピアメンター)制度(学部4年生、大学院生「留学生を含む」、卒業生、修了生)、AD(アドバイザーディベロップメント)(FD・SD、PMの採用と育成等)、生成AIアドバイジングシステムが3本柱とした。
こうした発表に対して、委員からは「小規模大学で対応できるのか」との質問があり、清水氏は「複数大学を回れるアドバイザーを作ること。AIの活用もデータが集まってくると活用しやすくなる」と回答した。
論点(1)、(2)を通して、委員からは大学教育の質向上・質保証には中等教育段階(高校普通科)でのキャリア教育の充実や質的向上、高大連携が大事で、大学側もどういう教育をしようとしているか、高校と丁寧なコミュニケーションが必要だ、とする意見が複数聞かれた。次回、第3回質向上・質保証システム部会は7月14日(月曜日)に開催する予定。最後に伊藤部会長は規制だけでなく、新しい試みを積極的に議論していきたいとの思いを明らかにした。