第1回地域大学振興有識者会議開催
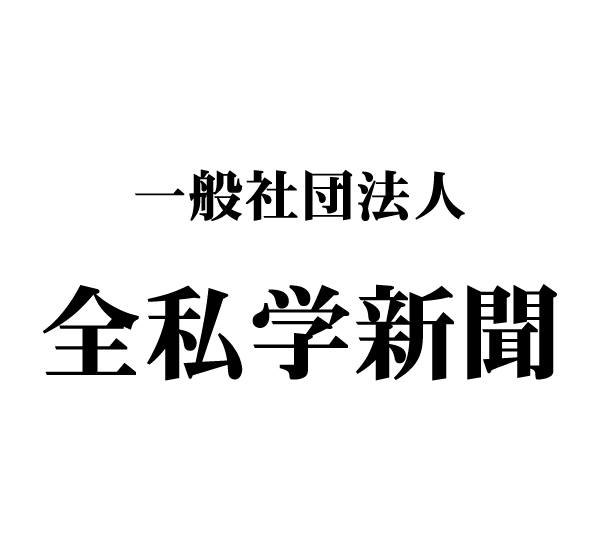
地方から高等教育アクセス確保
委員に学生も、地域大学振興等を議論
文部科学省は4月21日に同省内で第1回地域大学振興に関する有識者会議をウェブも併用して開催した。
同会議は令和7年2月に出された中央教育審議会答申の「我が国の『知の総和』向上の未来像」の提言等を踏まえ、地方からの高等教育へのアクセス確保や地方創生など地域大学振興の在り方を総合的に議論するのが目的で、担当は高等教育局大学振興課地域大学振興室。
座長には大森昭生・共愛学園前橋国際大学・短期大学部学長が選任された。また、特別委員として、共愛学園前橋国際大学、山梨大学、愛媛大学の学生がそれぞれ2人ずつ加わっている。
オブザーバーとして総務省、経済産業省も参加し、議題に応じて金融庁、厚生労働省、国土交通省、こども家庭庁なども出席することになっている。
最初に文科省から「知の総和答申」を踏まえて議論が必要な事項の説明があった。「知の総和答申」では、少子化により大学進学者数が減少するため、目指す未来像の実現のためには、知の総和(数×能力)を向上させることが必須とした。地域の高等教育のアクセスを確保するために、人材育成のための協議体「地域構想推進プラットフォーム(仮称)」、大学等連携を緊密にするための「地域研究教育連携推進機構(仮称)」の導入を提案している。
そして高等教育の制度改革や財政支援の取り組み、今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的方策に速やかに着手するとしている。政策パッケージ作成に向けて、本会議での論点として、地域構想推進プラットフォームの役割や整備促進方策、大学等連携推進法人制度の充実、発展、地域の高等教育へのアクセス確保、地方創生の取り組みに関する必要な方策等を挙げた。
続いて大学の地域連携、特別委員の大学生による地域での学びなどの発表があった。
洲本市(兵庫県)企画情報部企画課・新エネ・域学連携係長・高橋壱氏は2013年から始めた域学連携事業について説明した。淡路島にある洲本市は、市内には高校までしかなく、高校卒業後は進学や就職で島外に出るため、一度島から出ると戻ってこない場合が多く、活力と賑わいが低下している、とした。そこで若者を都市部から呼び込むため始めたのが域学連携事業で、大学生を洲本市に来てもらい、地域住民とともにまちづくりを行う。市職員2人で対応し、学生の交通費は予算の範囲内で市が負担し、学生が無料で滞在できる宿泊施設を用意している。
連携大学の一つ龍谷大学(京都府)は再生可能エネルギーの活用による地域活性化をテーマとして掲げ活動している。龍谷大学、洲本市、淡路信用金庫、淡陽信用組合、PS洲本株式会社(龍谷大学の教員が創設した発電会社)の5者は「地域貢献型再生可能エネルギー事業」を推進し、協定を締結。市内2カ所の農業用ため池に太陽光発電所を設置した。売電収益の一部は地域に還元し、地域活性化に活用されることになっている。売電利益を生かしてソーシャルビジネスのリサーチ拠点や社会起業家育成拠点が設置された、などと報告した。
共愛学園大学前橋国際大学国際社会学部4年の齋藤舞奈さんは、地方大学で学ぶ意義について発表した。齋藤さんは中高時代の地域ボランティア活動で地域と関わる面白さを知り、地域活動に積極的な同大学に入学した。大学では後期の授業で市内の企業や前橋市役所でインターン生として勤務し、前橋市役所の生涯教育課でイベントの企画運営業務に携わった経験を持っている。ゼミでは自分のフィールドを持ち、その地域の課題を見つけ解決策を考えることになっており、自身でこども食堂を立ち上げた。地域の住民やスーパーマーケットなどから支援を受け運営し、多拠点化も計画している。齋藤さんは「経済的な面から県内の地域と関わりの強い国公立大学を受験したが、希望が叶わず、群馬県内の私立大学で地域系の取り組みに力を入れている共愛学園を選んだ。県外進学は経済的に無理だったので、共愛学園がなければ大学進学自体を諦めていた」と話し、高等教育のアクセスを可能にする地方大学の存在意義を自身の体験から語った。次回は6月10日開催。


