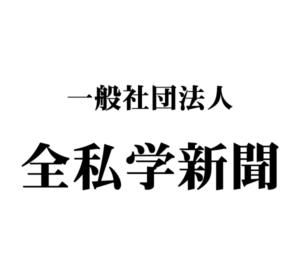光華女子学園の取り組み

令和8年4月から全設置校で男女一貫教育実施体制へ
京都一Well―Beingな人と社会共創
学校法人光華女子学園(京都府京都市)は教育体制の大幅な改革を進める。令和8年4月から、設置している大学・短期大学部・大学院・中学校・高等学校を男女共学化し、幼稚園から大学・大学院までの全ての設置校で男女一貫教育を実施できる体制に移行する。
学園名は「光華学園」に、大学・短期大学部・大学院は「京都光華大学」「京都光華大学短期大学部」「京都光華大学大学院」と名称を変更する予定となっている。同月には大学に「社会学部社会共創学科」(仮称・設置構想中)を開設する予定で、幅広い社会科学的手法で、持続可能な共生社会の創造に貢献できる人材を育成していく。
同学園は昭和15年の創立以来、建学の精神である仏教精神による人間教育を行い、多くの有為な女性を世に送り出してきた。社会情勢が大きく変化するとともに、男女の進学率はほぼ同等となり、同学園の取り組みが社会に影響を与え、女性の学習機会を拡充するという創立当初の理念が実現されてきた一方、現代社会では価値観の相違や経済格差等による「分断」、持続可能性確保といった課題が生じている。
こうした中、創立85周年を迎える同学園では、「Well―Beingな社会を創る」という願いを掲げ、あらゆる価値観を持つ人々が共に学び高め合い、共に輝く社会の実現に向けた人間教育と、共創する人材育成を行うために男女共学化を決断。男女の隔てなく全ての人間を対象とする仏教精神の原点に立ち戻り、同学園の伝統である「まじめさ」「寛容さ」「落ち着きのある安全な環境」を大切にし、新しいタイプの共学校を創っていく。
同学園では今回の男女共学化で幼稚園から大学までの一貫教育が可能となるため、幼稚園から大学まで同一敷地内に設置されている同学園ならではの特色を最大限に生かし「つながり、つなぎ、つないでいく」を合言葉に、これまで以上に密接な連携を実現させ、一貫教育のさらなる充実を図る。
幼少期から大学までの継続的な学びを通じて生き方の軸を定め、知識と実践力を兼ね備えた人材を育てることでWell―Beingな社会の実現に向けた多くの人材を輩出していく考え。▽実践的な宗教教育を通じて自らの生き方を問い直し、人生を豊かにする視点の養成▽文理両面(国・数・理)を特徴とする理系教育を導入し、知識をバランスよく習得できる環境の整備▽「光華SEL教育(Social and Emotional Learning)」を通じた主体性・協調性・表現力の育成と社会性の向上▽日常会話レベルの英語力の習得と国際社会でのコミュニケーション力向上▽AIをはじめとする先進的ICTの活用力と倫理観の養成、デジタル社会で活躍するための実践力向上―に取り組んでいく。
社会学部社会共創学科は現キャリア形成学部キャリア形成学科を発展的に改組して設置される予定。「共創」とは、多様性を理解し、異なる視点や考え方を受け入れ、持続可能な社会を「共に創る」という意味を持つ。
新学科は、多岐にわたる社会問題の解決に取り組むだけではなく、人と人、人と地域、地域と世界をつなぎ合わせて、社会に「新しい価値」を生み出す学科として「共創」を合言葉に、地域、文化、データサイエンス、経営、ウェルネスなど複数分野を横断複合的に学び、さまざまな特徴を持った個々のアイデアや強みを掛け合わせ、より良い社会(Well―Beingな社会)を形にすることを目指す。
新学科の設置構想に伴い、令和8年度以降、人間健康学群の学生募集を停止し、その定員と教育内容を新学科へ発展的に統合する。社会的ニーズの高い福祉・健康分野の学びを加え、さらに既存の他学部他学科との学びの連携を可能にする「ハブ的役割」を担う学科として、新学科を設置することで、同大学の目指す「健康・未来創造キャンパス」の充実に向けた改革を推進し、Well―Beingな社会の創造に向け、まい進していく。
3月12日に同大学慈光館で開催された記者会見には、同学園の阿部恵木理事長、京都光華女子大学・短期大学部の高見茂学長、京都光華中学校・高等学校の澤田清人校長、光華小学校の河原聡子校長、光華幼稚園の永本多紀子園長が出席。阿部理事長は「現代社会の多くの課題は『私=凡夫(消し難い煩悩と共に生きるただの人間)』に問われている課題だと理解した一人一人が、社会を変えていく意思を持って共創を始めたとき、社会は変わり始め、Well―Beingに近づいていく。京都光華は、STAYBONBU,CO-CREATWELL-BEINGを掲げ、京都一Well―Beingな人と社会を共創する学園を目指す」と意欲を示した。