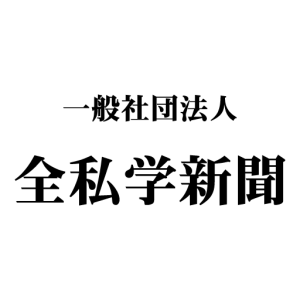中教審総会、文科相から学習指導要領の改訂など諮問

教職課程の在り方も見直しへ
文部科学省は令和6年12月25日に中央教育審議会(会長=荒瀬克己・独立行政法人教職員支援機構理事長)の第140回総会を対面とウェブを併用して開催した。
総会では文部科学大臣から2件の諮問があった。1件目は学習指導要領の改訂で、審議事項が4点提示された。1点目は、デジタル学習基盤を活用した質の高い、深い学びを実現する、分かりすく使いやすい学習指導要領の在り方。2点目は標準授業時数の柔軟化など、柔軟な教育課程編成の促進、不登校や特定分野に特異な才能を持つ児童生徒などへの教育課程上の特例など、多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の検討など。
3点目は各教科やその目標・内容で、情報活用能力の抜本的向上を図る方策、文理横断・融合の観点からの初等中等教育の改善など。4点目は学習指導要領の趣旨の実現のための、過度な負担とならない学習指導要領などの在り方、現在以上に増加させないことを前提とした年間標準総授業時間の在り方など。
この諮問に関連して、中教審委員からは「現在の教育システムは複雑にからみ合っている。バランスを大切にして多角的、多面的な議論が必要」「現行の学習指導要領の浸透が道半ばと諮問文にあるが、現場の先生と対話を続け、プロセスも重視しながら議論してほしい」などの意見があった。
2件目の諮問は、教師不足に対応する、多様な専門性を持つ質の高い教職員集団の形成のための方策で、主な検討事項は3点。1点目は教職課程の在り方、教員免許制度の在り方、教師人材確保の取り組みなど。2点目は教師の質を向上させるための採用・研修の在り方で、教員採用選考の共同実施など採用に関する方策、教師の資質能力を高められる環境の整備など。3点目は専門性を持つ社会人が教職へ参入しやすくする制度の在り方で、特別免許状の活用促進、企業等に在籍しながら教師として勤務する際の任用形態など。
この諮問に関連して委員からは、「質の高い人材が学校で働き続けるためには、過剰な事務作業を削減させることが急務」「企業で働く人の中には教師の仕事に興味を示す人がいるが、企業はどこから手をつけていいのか分からない。マッチングへの支援も必要」「教師の資質向上の方策だけでなく、職場環境、人間関係の構築の支援も必要」などの意見が出された。
続いて、総会では大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会でまとめられた「急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について」の答申案が報告された。
答申案では高等教育が目指す姿を、わが国の「知の総和」(数×能力)の向上とし、その実現のためには教育研究の「質」を上げ、社会的に適切な「規模」の高等教育機会を供給し、地理的・社会経済的観点からの高等教育の「アクセス」の均等を図る、としている。
具体的方策として「質」の高度化には、厳格な成績評価など出口の質保証、在学中にどれだけ力を伸ばすことができたかなどで評価する新たな評価制度への移行、通信教育課程の質向上のための制度改善等、また大学院教育の改革として高等教育機関の情報を横断的に比較できる新たなデータプラットフォームの構築などを挙げている。
「規模」の適正化には、厳格な設置認可審査への転換、再編・統合の推進などの方策を提言。
「アクセス」の確保の方策には、地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界が議論する「地域研究教育構想推進プラットフォーム(仮称)」の構築、大学などの連携を緊密にするための「地域研究教育連携推進機構(仮称)」の導入、遠隔・オンライン教育の推進、個人への経済的支援の充実などを挙げている。
制度改革や財政支援の取り組み、今後10年程度の工程を示した政策パッケージを策定し、具体的な方策に速やかに着手できるようにする方針だ。
この答申案に対して意見が求められ、委員からは、「政策パッケージには優先順位をつけ、3~5年ごとに検証が必要」「将来の人材育成には高等教育を担う人材の育成も必要」「単科大学が自前で文理横断・融合を行うのは難しい。プラットフォーム内で他大学の講義を提供できるとよい」「高校での早期の文理分断は問題。大学入試の課題にも踏み込みたい」「今の高校生に課せられている教育課程では高校2年から文理分けをしないと大学入試に対応できない。大学教育を受けられる子供をどれだけ育てられるか、文科省の部署を越えて考える必要がある」などの意見が出された。
答申案はパブリックコメントに付された後、引き続き審議される。