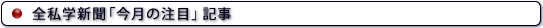
TOP >>
バックナンバー一覧 >> 2005年9月3日号二ュース >> VIEW
記事2005年9月3日 1990号 (2面)
義務教育費国庫負担制度で意見聴取
ほぼすべてが堅持主張
【義務教育特別部会】
中央教育審議会義務教育特別部会(部会長=鳥居泰彦・慶應義塾学事顧問)は八月二十四日、都内で会合を開き、七月にまとめた審議経過報告について、関係四十三団体から行ったヒアリングと一般からの意見募集の結果を公表した。同部会で最大の検討課題となっている義務教育費国庫負担制度の存廃については、三十四団体から意見表明が行われ、うち制度を堅持すべきとの意見は三十一団体、確実な財政措置を行うべきとの意見が二団体、その他の意見が一団体だった。一般からもほぼすべてが制度堅持の意見だった。
堅持の立場からは「全国的な教育水準の維持向上と教育の機会均等を保障する上で、この制度は重要な役割を果たしている」「この制度により、都道府県間の教員配置や給与水準が一定に保たれている」「義務教育の根幹であり、国がしっかりと責任を負うべき」との趣旨の意見が多かった。
ほかにも「全額国庫負担が望ましい」「地方の使い勝手を良くするためには、一般財源化でなく、総額裁量制の改善を図っていくべき」「税源移譲によって教職員の教育への意欲が変わることはない」「国庫負担制度は地方分権を阻害しない」などの意見もあった。
また確実な財源措置を求める立場からは、「義務教育制度の根幹を維持し、教育水準の維持向上のために確実な財源保障が不可欠」「地方交付税については総額を抑制する動きもあり財源確保に対する懸念は否定できない」などとしている。
一方、その他の意見では「三位一体改革を支持するが、義務教育に関する財政の具体論については、今後一層議論を深めたい」と明言を避けるものもあった。一方、七月二十日から八月十日まで実施したパブリックコメントには八千七十九件の意見が寄せられた。だが、意見提出者の約七割を教員が占めている。
それによると、約九割が国庫負担制度について触れていて、ほぼすべてが「堅持」の結果となった。理由として「一般財源化すれば多くの県で財政確保ができず、地域間格差が生まれてくる」とする意見が多かった。
会合ではこれらの結果に対し、石井正弘岡山県知事が「ヒアリングは教育関係団体に偏っている印象が強い。もっと幅広く聞いてほしい。一般意見も教育公務員の意見を割り引いて分析されるべき」とけん制した。
他方で、平成十九年に小中学校の高学年で悉皆実施とされている「全国学力調査」の導入について、藤田英典・国際基督教大学教授は「学校の序列化を招き費用の面でみても弊害の方が大きい。抽出調査でも対応できるのではないか。何のメリットがあるのか検証していかなければならない」などと主張。
銭谷眞美・文科省初等中等教育局長は、十八年度概算要求に学力調査の検討、準備のための諸経費を盛り込むことなどを説明した。
「新時代の大学院教育」答申へ
【大学分科会】
中央教育審議会大学分科会(分科会長=相澤益男・東京工業大学長)は八月二十五日、都内で会合を開き、大学院部会が八月二日にまとめた「新時代の大学院教育――国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて」の答申案について議論したほか、高等専門学校設置基準を一部改正し、四十五時間の学修を一単位とする計算方法を導入することを決めた。
会合では、答申案について「外国からの留学生もいることから論文博士の制度を直ちに廃止するというのは無理」(井村裕夫・京都大学名誉教授)「学生自らがクリエーション、トレーニングしていける場にしなければならない」(安西祐一郎・慶應義塾長)などの意見があった。九月五日に開かれる中教審総会で答申される予定だ。
一方、同部会では今年一月に答申された「我が国の高等教育の将来像」を踏まえ、高等専門学校設置基準を一部改正することを決めた。
高等専門学校では、これまで三十時間の履修を一単位として計算されていたが、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容を標準とし、講義および演習については十五時間から三十時間までの範囲、実験・実習・実技については三十時間から四十五時間までの範囲とする。それぞれの高等専門学校が定める時間の授業をもって一単位と計算できるようにすることで、実験系科目の充実や新たな科目の開設など各高専の創意工夫でカリキュラム編成が可能となる。今月中に施行、公布の予定となっている。
教育課程の基準等検討
全国学力調査では賛否
【教育課程部会】
中央教育審議会初等中等教育分科会の教育課程部会は、七月二十五日、八月二十二日にそれぞれ第八回、第九回部会を開き、教育水準の維持向上のための方策、学習指導要領等の教育課程の基準等のあり方などについて討議した。子どもたちに求められる学力や総合的な学習の時間の扱い、学校週五日制の扱いなど総論的な検討を行い、現在明確ではない到達目標をどうするのか、目標に達しない児童生徒の扱いなどが話し合われた。第九回では評価方法と絡んで全国的な学力調査実施の是非が議論され、委員からは賛否両論が出され、結論には至らなかった。
次いで八月二十九日の第十回部会では、政府の「骨太の方針二〇〇五」に推進が明記された食育、キャリア教育、金融経済教育について有識者から意見聴取した。これらの教育は新学習指導要領に反映される予定。
|
記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
|