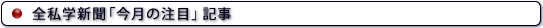
TOP >>
バックナンバー一覧 >> 2001年2月23日号二ュース >> VIEW
記事2001年2月23日 5号 (6面)
インタビュー
司法制度改革審議会会長代理 竹下 守夫 氏 駿河台大学学長
司法制度改革審議会がまとめた中間報告では、法科大学院の設置の必要性を打ち出した。竹下守夫・同審議会長代理(駿河台大学長)に法科大学院構想の課題などを中心に伺った。
―司法の現状についてどのような認識をお持ちですか。また、司法改革の必要性についてはどうお考えですか。
会長代理 一般的なことからお話しします。我が国は明治以来、行政が中心となって国づくりを行ってきましたが、いま透明なルールによる社会統制が求められています。民主制の社会では透明なルールが社会の隅々まで貫徹されることが重要となります。角度を変えれば、司法が民主制の中核となる役割を担うということです。
もう一つは司法も国際的な役割を担っているということです。つまり、情報社会での国際的なルールづくり、あるいは外国人や企業が司法制度を利用しやすいようにすること、さらに司法分野での発展途上国への支援などの国際貢献が考えられます。
このような観点からみれば、司法の改革については制度的基盤、人的基盤、国民的基盤という三つの柱から考える必要があります。制度的基盤の点については、国民が司法を利用しやすいことや、裁判費用、裁判の迅速性などの面で司法制度を構築することが重要です。人的基盤については、法曹の質と量の両面から問題になります。中間まとめでは、計画的にできるだけ早期に三千人程度の新規法曹の確保を目指す必要があるとしました。国民的基盤については、現在の憲法体系では国民主権からストレートに国民が司法に参加できるということにはなりませんが、司法参加の充実は望ましいことです。その形態としては陪審制、参審制が考えられますが、法律家と、一般人とのコミュニケーションを深めるという方向が大切です。
―大学の法学教育の現状と問題点は。
会長代理 大学法学部卒業生の大半は法曹を目指さないということで、従来は法曹養成という視点が欠けていました。また日本では研究者養成課程と実務家養成課程とが分離していましたが、研究者を大学で純粋培養するという点も法学教育のあり方のひとつの問題です。
―法科大学院構想についての問題点は。
会長代理 法科大学院構想の出発点は質を向上させながら、量を増やすことにあります。質の向上を図りながら量を増やすという観点からは、日本の現状では法科大学院構想以外の選択肢を考えるのは困難です。問題は私学にとっては財政的負担、受験生にとっては授業料などの費用の増加という、コストの面です。これに対しては、連合大学院、夜間大学院という方法、大学院設置基準にいう専門大学院とは異なる設置基準の導入学習ローンなどが考えられます。
また、例外措置として、法科大学院を卒業しなくても法曹となれる道を開く必要があるのではないかと思います。
具体的な問題として、実務家教員の確保の点ですが、非常勤講師では無理があります。将来的には法科大学院卒業の人が教員となることを考えるべきでしょう。当面は臨時の措置が必要です。
―国民に信頼される法曹像とは。
会長代理 中間報告では法曹を「国民の社会生活上の医師」と位置づけています。ここでは人間性への理解を持つという意味が含まれています。私はこの点について異論はありませんが、やはり専門的な卓越した法的知識や判断力が必要です。国民からみて、まず身近な弁護士を中心に法曹像を考える必要があると思いますが、裁判官や検察官も国民とのかかわりがあることを考えれば、清廉潔白性、中立性が要求されることも見落としてはいけないと思います。
今後、法曹界に進む人はどのような心構えを持つべきでしょうか。
会長代理 これからの司法の役割の重大性と国民に対して責任を負うということを自覚した人に法曹になってほしい。今後さまざまな面で変化の激しい時代を迎えますが、何が守られるべき法的価値かについて鋭い感覚を持つ必要があります。それとともに、法律的判断として一般人が納得するように法的に構成する力を身につけることが重要です。 |
記事の著作権はすべて一般社団法人全私学新聞に帰属します。
無断での記事の転載、転用を禁じます。
|